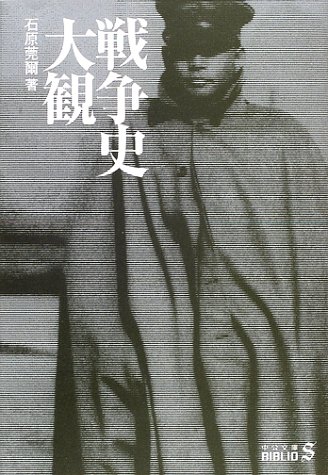クールなリアリストの素顔
いま聞けば、荒唐無稽なとんでもない話である。しかし、石原の戦略構想を当時の国際情勢や時代背景の文脈において考えてみれば、気宇壮大なナショナリストの大言壮語で片づけられないものがある。石原はきわめて熱いナショナリストである。しかしその裏側には、クールでロジカル、リアリズムに徹した戦略思考の持ち主という正反対の顔があった。
たとえば、石原の時代に先行する日露戦争に対する見解である。陸軍の指導者だった若い時分から、日露戦争の大勝利はどう考えても僥倖だったと石原は考えていた。ロシアがもう少し実力を出せていたら危なかった。根本的な問題は、日露戦争に「全体の構想」がなかったことだと指摘している。日本は日露戦争で『坂の上の雲』に描かれているような歴史的勝利をおさめたわけだが、しょせん現場の作戦計画が当たっただけで、背後に国防の大方針があるわけではなかった。もし第一会戦を落としていたら、なし崩し的に敗北したであろう、というのが石原の見解である。
彼はさらに考えを進める。大構想を持たずに作戦計画だけで戦った日露戦争で勝ったのは運がよかったにすぎないと結論しつつも、逆に大構想があったら、そもそもロシアを相手に戦争などできなかっただろうとも言っている。勢いや情のような理屈では説明できないものと、歴史から導出された骨太のロジックの両方が常に見えているのだ。この辺、非常に客観的で、覚めた思考をする人である。
石原に限らず、優れた戦略家のなかにはホットなパッションとクールなリアリズムが常に同居している。徹底的にロジカルでなければ、ロジックで説明できないことの輪郭もつかめない。『最終戦争論』でのパッションの爆発も、その背後に冷徹なリアリストの眼があったからこそだといえるだろう。
石原がリアリストであったことは、『最終戦争論』の講話をした1940年当時、つまり日本が大東亜共栄圏だといって盛り上がっている最中に、「現状は東亜大同から程遠い。それが証拠に兄弟たるべき東亜の国々から蛇蝎のごとく嫌われているではないか」と明言していることからもわかる。東洋の王道文明たるべき日本が、勝手な都合で短期の利を求めている、西洋覇道文明にかぶれて功利主義に走りすぎだ、大反省するべきだ、と冷静に認識している。
石原が『最終戦争論』の講演をして間もなく、日本は統帥権が独立していたのをいいことに、天皇を担いで軍部が勝ち目のない持久戦争、太平洋戦争に突入した。石原はこの統帥権独立が持久戦争にとっては仇となるということについても早いうちから警鐘を鳴らしている。統帥権が独立しているほうが有利なのは、短期に相手を殲滅しうる決戦戦争に限られる。持久戦争を遂行するためには政治による文民統制が敷かれていなければならない、というのが石原の主張である。
石原はさらに興味深い思考実験をしている。統帥権が独立している日本が持久戦争に突入してしまうと、軍部が暴走し、引くに引けないという難局に陥る。しかし、日本に唯一の救いがあるとすれば、ほかのヨーロッパの国と違い、天皇という独特の統治者がいるということだ。最後の最後には天皇の聖断で戦争に終止符を打つ可能性が残されていると指摘している。太平洋戦争の開戦から終戦に至る経緯として、これは実際に起きたことに驚くほど近い。