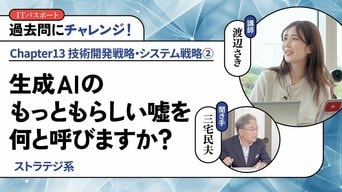なぜ「創って作って売る」なのか

「スモール・イズ・ビューティフル」。三枝さんの唱える題目である。「創って作って売る」のリーダーに当事者として自分のまかされた商売の戦略ストーリーを考えさせる。それを三枝さんがトップ経営者として満足いくまで叩きまくる。いけそうだなと思えるレベルになったら完全に実行を任せる。これを繰り返すことによって、ユニットのリーダーは、戦略立案の方法論を学び、人使いに慣れ、損得責任を負うことの辛さを肌で知ることになる。
「創って作って売る」を経営の単位とする理由は、「一人の経営リーダーが自分の事業を生き生きと保てる組織規模」を維持することにある。経営が成長を志向する以上、規模の増大は必然である。しかし、大企業になると、事業ユニットが大きすぎて一人のリーダーの手に負えなくなる。「創って作って売る」が一気通貫しているはずの商売が担当業務へと分かれてしまう。社長の指示待ちの担当者ばかりになるという成り行きである。俗にいう大企業病の成り行きである。三枝さんがミスミでやっていることの一つの本質は、放っておいたら自然と壊れてしまう「商売丸ごとの塊」を経営トップの意図とデザインで会社の内部に確保する生み出すことにある。
「創って作って売る」ユニットは、あくまでもタテの事業ラインでなければならない。「タテ」の意味は、経営の結果責任を負うということだ。小規模でも、経営に必要な機能はすべてそろっているのが前提である。自己完結的なユニットを数多く用意すれば、資源が重複し、規模の経済が損なわれるのは言うまでもない。そのギリギリのバランスをとる絶妙のさじ加減、ここに三枝さんの本領がある。
たとえば、「創って作って売る」ユニットをたくさんつくると、これまで一つだった機能部門を分散させる必要が出てくる。そこで生じる非効率は「指示系統では分かれていても、物理的には同じフロアに置いておく」ことで補完する。こうした工夫は枚挙にいとまがない。この辺の手当てのユニークさ、手数の多さが三枝さんの「経営者が育つ土壌の経営者」としての真骨頂であり、読んでいて実に面白い。