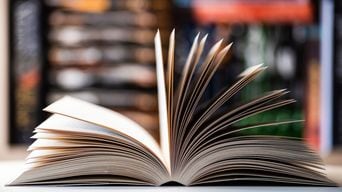「女性天皇」容認を示した世論調査
毎日新聞では、今年5月に皇室についての世論調査を行った。それによれば、皇室への関心の有無を聞いたところ、「今の皇室に関心がある」は「大いに」と「ある程度」を合わせて66%にのぼった。「あまり」と「全く」を合わせた「関心がない」が33%だから、その2倍に達したことになる。
およそ3分の2が皇室に関心を持っていることになるが、18歳から29歳までの若年層になると、関心があるが50%まで低下している。関心がないが49%だから、それはわずかに上回っているものの、若年層の皇室への関心は薄いと言わざるを得ない。
女性天皇については、それを支持すると答えたのが全体の7割にのぼった。一時、女性天皇を支持する声が9割を超えたこともあった。ただし、悠仁親王が誕生したことでその数字は下がった。重要なのは、今回の調査で女性天皇を否定したのはわずか6%だったことである。女性天皇を容認する声が大多数を占めていることになる。
こうした調査が行われたのも、開会中の国会で皇統の安定的な継承、皇族数の確保について議論が進められていたからである。これについては、今回は先送りになってしまったが、喫緊の課題であることは間違いない。
「天皇不在」で機能不全に陥る日本
なぜ皇統の安定的な継承ということが問題になってくるのか。
端的に言えば、万が一「天皇不在」という事態が起これば、日本の国はフリーズし、機能不全に陥ってしまうからである。世論調査でも尋ねてほしいところだが、そのことを理解している国民は意外に少ないのではないだろうか。
その点については、拙著『日本人にとって皇室とは何か』でも説明した。日本国憲法によって天皇は「国事に関する行為」を行わなければならないと定められている。
もちろん、天皇が勝手にそれを行うわけではない。内閣の助言と承認を必要とするのだが、国会の指名にもとづいて内閣総理大臣を任命すること、内閣の指名にもとづいて最高裁判所の長たる裁判官を任命することからはじまって、次のような国事行為が定められている。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
一見してわかるように重大なことばかりである。
これはまったくの架空の話だが、今この瞬間に天皇不在という事態が起これば、そうした重大なことがすべてできなくなる。