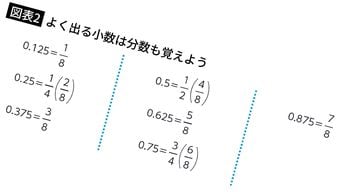※本稿は、宇野仙『日本史と地理は同時に学べ!』(SBクリエイティブ)の一部を再編集したものです。
地理を学べば、歴史がもっと理解できる
「歴史の勉強をする際に、歴史の教科書だけで勉強してはいけない」と言われたら、みなさんはどう思うでしょうか? 多くの人は「何を馬鹿なことを」と思うかもしれませんが、しかしこれは実際に日本史や世界史を深く勉強している人であれば誰もが頷いてくれることです。
歴史の勉強には、地理的な要因が深く関わっていることがあります。世界地図をしっかり理解していなければ、いくら世界史の勉強をしても頭に入ってくるわけがありません。江戸や大阪が地理的にどのような優位性があったのかを理解していなければ、江戸時代の勉強をしていても理解できない部分が多いです。
江戸時代の人口規模がわからない状態で江戸時代の勉強をしても、半分くらいしか理解し切れないのです。もし日本史の勉強や世界史の勉強で躓いてしまったとしたら、それは歴史がわかっていないのではなく、地理を理解していないからかもしれないのです。
重要なのは、日本史と地理を融合した形で学んでいくことだと言えます。今回はいくつかの例を挙げて、日本史の疑問は、地理の知識があれば解消でき、理解が深まることをみなさんに共有したいと思います。
“最強の戦国武将”には、土地が不足していた
例えば戦国時代の勉強をしていると、「戦国最強の武将は誰か?」という問いを考えることがあるのではないでしょうか。
この問いに対して、上杉謙信や武田信玄の名前を挙げる人は多いかもしれません。武田信玄は、甲斐の国・現在の山梨県の戦国大名で、「甲斐の虎」と呼ばれました。信玄の率いる武田の騎馬隊は、戦国時代において最強と謳われていました。
しかし、信玄は天下を取ることができず、最終的に織田信長・豊臣秀吉が天下統一を果たします。なぜ、軍事的に強かったにもかかわらず、武田信玄は天下統一を果たせなかったのでしょうか?
もちろん、さまざまな要因が複雑に絡み合った結果ではあると思いますが、実はこれに関しては、地理的な視点で見ると1つの重要な事実が浮かび上がります。それは、「土地の問題」です。
まず、甲斐の国は農地が弱く、水害の多い地域でした。そのうえ、内陸にあったため、水運を使った交易ができず、商業があまり栄えませんでした。織田信長の領地の農業生産性はかなり高かったと言われており、かつ、水運で経済的にも成功していたことを考えると、かなり対照的です。