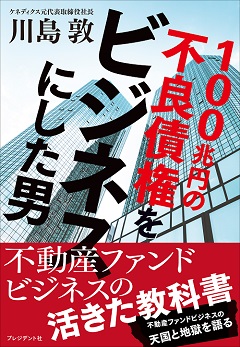「土地神話」に基づく不健全な循環モデル
今では考えられない話だが、高橋治則が乗ったバブルとはいったい何だったのか。煎じ詰めれば金融緩和を背景とした「金余り」、そしてその余った金を吸い込んだ「土地神話」に帰結する。1985年のプラザ合意、1986年からの金融緩和で市中にだぶついたマネーが土地と株式市場(マーケット)に雪崩れ込んだ。株高は企業や個人の信用余力をかさ増しし、底上げされた信用力を担保に銀行はお金を貸し、そのお金がまた土地に回った。
「日本の土地は必ず上がる、土地さえ買っておけば間違いない」。理屈も何もない。土地は上がる、上がるから買う。買うからまた上がる。この循環だった。だぶついたお金を抱え貸出先を探す銀行は、これまでなら考えられない相手に深入りする。長銀がEIEの高橋治則にのめり込んだように、三井信託銀行と麻布建物の渡辺喜太郎、日本興業銀行と大阪ミナミの料亭経営者の尾上縫が関係を深め、名門銀行の資金が、土地の信用をバックに闇に消えた。
それには土地は上がらなければならなかった。デューデリジェンスも何もない。そんな言葉もなかった。
「デタラメな時代」も長くは続かなかった
今なら土地から上がる収益をもとに土地の値段は決まる。土地の上に立っているオフィスの賃料は坪(3.3平方メートル)あたりいくら、延べ床面積はどのくらい、共用部分を除いた賃貸面積がどのくらいで、年間いくらのお金が入るから、このビルの価値はいくら、あるいはこの土地の価値はいくら、と算定される。それが普通だ。不動産から上がった収益は不動産に投資した投資家とアセットマネジャーに約定通り分配される。ケネディクスのような不動産のアセットマネジャーがバブルが崩壊した後に、米国から学び、取り入れた。
バブルの時代はそうではない。土地は上がるから上がった。「土地の収益性」という頸木を持たなかった東京23区の土地の値段は、米国全土の2倍の価格と並ぶ水準にまで上がった。さすがに1989年には政府もその異常さを指摘せざるを得ず、年次経済報告(経済企画庁)では「バブルが発生していた可能性」について触れている。誰もが内心、長くは続かないと気づきつつブレーキを踏めずにいた。
しかし、デタラメな時代も長くは続かなかった。1990年3月に大蔵省(現・財務省)が発した土地関連融資抑制の通達、いわゆる総量規制と地価税、そして日銀による公定歩合の引き上げで、金融の蛇口が締められ始めると状況は変わる。経済の歯車は逆回転を始め、土地の値段は急降下し始めた。そしてバブルは崩壊した。