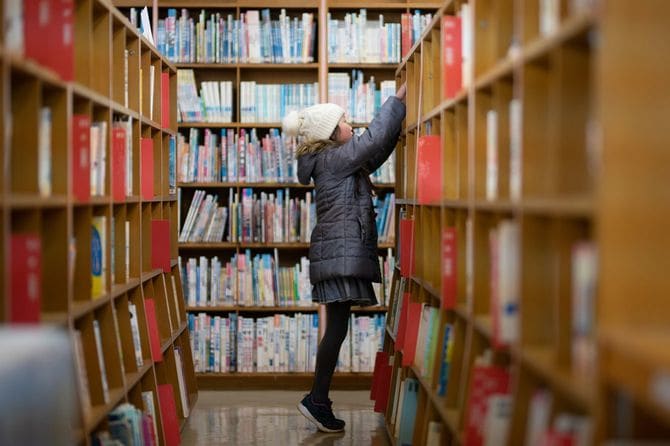※本稿は、小島俊一『2028年 街から書店が消える日 本屋再生!識者30人からのメッセージ』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。
「販売の生命線」が絶たれる衝撃
世の中の方々には、「コップの中の嵐」に過ぎないでしょうが、昨年、出版界というコップの中で大きな嵐が起こりました。
コンビニの雑誌は取次の日販やトーハンが物流と決済機能を担っています。日販はローソン・ファミリーマートと取引があり、トーハンはセブンイレブンと取引があります。そんな中、日販が2024年にローソン・ファミリーマートとの取引を中止するという話があり、それが出版社に伝えられました。日販にとって大きな赤字部門であるコンビニとの取引から撤退したい強い意向が示され、出版界は大騒ぎになりました。
本稿では、この顛末と共に「街に書店を残す処方箋」の一部をお伝えします。
出版社にとって、コンビニの雑誌販売は広告料収入の面から言っても、雑誌販売の生命線です。その中でローソン・ファミリーマートの販売占有は大きく、この販売ルートを失うことは、出版社にとって大打撃になり、雑誌存続にも関わります。
日販の奥村景二社長は、「コンビニルートの2023年度売り上げは280億円で赤字が40億円にもなる見通しだ」と話されています。日販全体としても2023年度通期でもかなり厳しい決算が見込まれています。この現状に鑑み日販はローソン・ファミリーマートとの取引辞退を決めたのでした。
「コンビニ配送のついでに書店に本を運んでいる」
これに対してトーハンは、川口雑誌新センターに42億円もの投資をしてでも取次事業を守り全国の書店に寄り添い続けるとして、ローソン・ファミリーマートとの取引は2025年7月から始めることになりました。
出版流通は雑誌配送が根幹になっています。特に全国に5万軒あるコンビニルートがその中心です。極端な言い方をすれば、「コンビニ配送のついでに書店に本を運んでいる」状態です。日販が手放したローソン・ファミリーマートとの取引をトーハンが引き継ぐのは、その使命感ともいえるでしょう。
日販はその後の物流をどんな風に構築されていくのか、大変に興味深いものがあります。物流系のコンサルタントが入っておられると聞いていますので、何らかの見通しはお持ちの上での決断かと思いますが、トーハンは雑誌配送を守りこれまでの流通ルートを守り、日販は新たな書籍を中心とした流通ルートを見据えているように思えます。
経営者が死力を尽くすトーハンと日販のどちらの経営戦略が正解なのかは、部外者が軽々に論ずることはできませんが、そう遠くない時期に結論は出ると思われます。