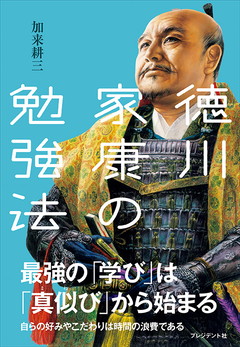有効だった「手紙作戦」
二男・結城秀康を上杉氏の押さえとして宇都宮に残し、家康は8月5日に江戸に帰着しました。
八方の形勢を見極め、できる策を施し、西上の機会をうかがうためです。
実際、小山を撤収して以来、家康は連日のように天下60余州の大名たちに、精力的に書状を送り続けています。
東軍参加の兵を募るとともに、すでに西軍に味方している者の翻意を促すためです。
外様の諸将宛てに出した書状は、現存するものだけで約160通、宛先は計82名といわれています。
家康だけでなく、家臣の本多正信や井伊直政、本多忠勝ら、そして家康派大名の黒田長政、藤堂高虎、細川忠興らも、これに数倍する量の書状を送っていました。
家康の懐柔による多数派工作は、三成の知らない間に大坂城の奥深くからも、それなりの成果を見せ始めていました。
公卿の広橋兼勝、観修寺光豊が、後陽成天皇の命を受け、秀頼を大坂城から出陣させないよう奔走していました。秀頼がひとたび親征の軍を発すれば、家康といえども勝ち目はなかったに違いありません。
勝敗のカギを握っていた2名
また、勝敗の鍵を握っていたといえる毛利一門の二人の武将、小早川秀秋、吉川広家への調略も成功の兆しが見えてきていました。
広家は、毛利元就の次男・吉川元春の三男で、輝元とは従兄弟にあたる毛利一門の重鎮であり、毛利家を取りまとめる軍事の中心的人物でした。
この戦の前年の1599年、広家は、天下衆目の中、五奉行の一・浅野長政と大喧嘩を演じたことで、一時は毛利家は取り潰しかとの風聞も流れるなか、家康と黒田官兵衛─長政父子のとりなしで助けられたことから、毛利家の戦闘参加を阻止する役割を果たそうとしていました。
一方の秀秋は北政所の兄・木下家定の五男に生まれ、3歳で秀吉の養子(猶子とも)、次いで小早川隆景(毛利元就の三男)の養子となった武将で、慶長の役において、朝鮮半島で軽率なふるまいがあったのを秀吉に咎められ、越前北ノ荘へと領地を左遷され、悶々とした日々を送っていた時期がありました。
秀吉の死後、それを家康によって、もとに戻してもらった恩義があります。
秀秋は毛利一門として西軍に属していましたが、秀秋率いる1万5000余の兵力の大きさから、家康の工作は小早川家の老臣・稲葉正成(のちに江戸幕府の3代将軍・徳川家光の乳母となる春日局の夫)を通じて、執拗に繰り返されていました。