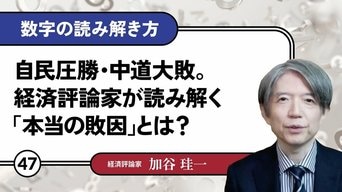「インバウンド客が押し寄せて常連が入れない」
Xの投稿で賛否を呼んだのが、東京都墨田区にある大衆酒場の店主のポストだ。内容は「英語で話しかけてきた白人カップルに日本語で回答した。日本を訪れたなら、日本語を話す努力をしろ」という主旨であった。その後、店主は「多くの人に不愉快な思いをさせ、自身も精神的にも肉体的にも仕事をする気力がないので休業する」という投稿をしている。
広島県にあるお好み焼き店は、テレビ番組の取材に対し、オーバーツーリズムに対する悩みを吐露。「インバウンド客が押し寄せて来て、常連客が利用できなくなった」と語った。苦悩の末に出した結論として、毎週金曜日の夜を「県民の日」と定め、自己申告ながらも県内に在住する人だけが入店できるようにし、訪日外国人を含む県外の客を断っている。
むろん飲食店と客のトラブルは今に始まったことではない。ただ、2016年に観光庁が「明日の日本を支える観光ビジョン」で、2020年に4000万人、2030年に6000万人という目標を掲げて以降、コロナ禍を除けば訪日外国人の数は増加の一途を辿っており、飲食店との間で“新たな事案”が増えているのだ。
飲食店と外国人はそれぞれ何に困っているのか
こうしたトラブルを整理すると、訪日外国人が困っているケースと飲食店が困っているケースに大別される。
訪日外国人が困っているのは、日本語オンリーでコミニュケーションができないという言語の壁、英語メニューの用意がなくてオーダーするのが難しいこと、理不尽に感じられる不明瞭で一方的なお通しの提供、ベジタリアンやヴィーガンといった信念あるいはハラルなどの宗教に則った食事の非対応、食べ残したものの持ち帰り不可がよく挙げられる。
2016年度に発表された観光庁による「訪日外国人旅行者の国内における受入環境整備に関するアンケート」では、多言語表示やコミュニケーションで困った場所として、飲食店が28.5%で1位。場面別では「料理を選ぶ・注文する際に困った」が65.8%、「飲食店を見つける際」が32.9%、「食べ方の説明を受ける際」が32.2%と続いている。
一方、飲食店が訪日外国人で困っていることは、一般的な日本人ではあまり見かけられないマナーや態度の悪さ、ノーショー(無断キャンセル)や直前キャンセルの発生率が高いこと、コンシェルジュなどの代行を除いた予約者とは異なる人物による利用が少なくないこと、異なる文化や慣習を持つ客に応対するスタッフの疲弊、殺到する一見客によって常連客が入れなくなることだ。
2018年に飲食店ドットコムが行った「飲食店における外国人観光客対応の課題」に関するアンケート調査では、訪日外国人に対する飲食店の課題がまとめられている。1位が「料理や食材の説明」、4位が「予約の受付」、5位は「会計に関する説明」とコミニュケーションに関するものが圧倒的に多い。そのほかは「店内でのマナー」(2位)や「苦手な食材の対応」(3位)が上位となっている。