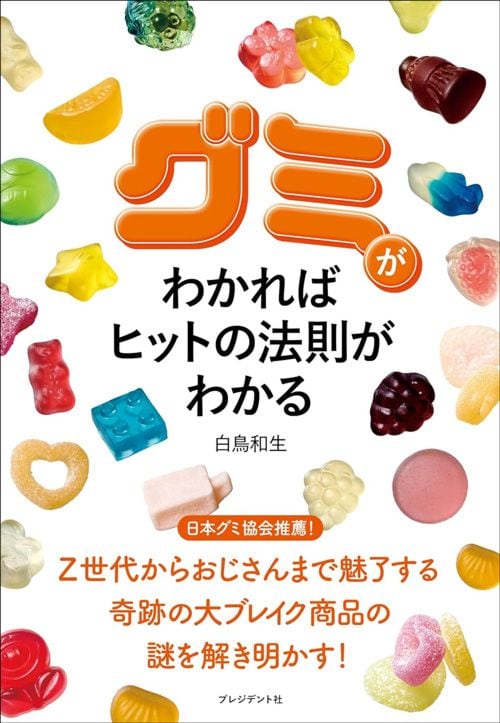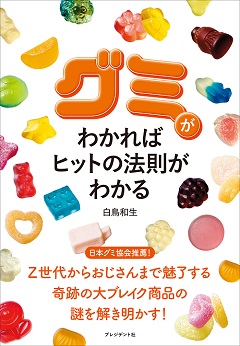商品数は370→800種類へ
グミは商品数が増えていることも、消費者へのアピールにつながっている。日経POSデータによると、2019年は約370種類だったが、輸入品も増えており、2023年8月時点では792種類と800種類に迫っている。
都内にある食品スーパーのバイヤーは「SKU(商品の最小管理単位)は拡大傾向にあり、今後も成長するカテゴリーと判断している」と話す。また、大手コンビニエンスストアの担当者は「店のレイアウト変更のたびに、グミは売り場を広げている。ガムは逆に、これ以上減らせないぐらいのところまで、売り場面積を減らしてきた。ガムは右肩下がり、グミは右肩上がりの構図は、コロナ禍で決定的になった」と見る。
また、カンロの村田哲也社長は「グミの購入率は、10年間で6ポイント程度しか伸びず、現在4割台。逆に飴の購入率は少し落ちているものの6割台。10代は、飴よりもグミを購入する傾向にあるが、10代以外の世代は飴を買う傾向にあり、グミはまだまだ伸びる余地がある」と見ている(2023年7月27日の中間決算発表会での発言)。
ガムは「ゴミが出る」が意外にネック
グミとガムを比較する場合、「ゴミ」との関係も無視できない。ガムが支持されてきたのは、かむと気分のリフレッシュや眠気覚まし、歯の健康への配慮といった便益があったためだ。だが、最近はガムのデメリットが目立つようになってきた。口からガムを吐き出すことに対するネガティブなイメージや、ガムのゴミを処理する煩わしさが増大した。特に街なかや駅構内でテロ対策などからゴミ箱が減っていることがある。
地球環境問題は政治経済の喫緊の課題となっている。国連が2015年に策定したSDGs(持続可能な開発目標)の認知が広がる中、ゴミの削減は生活者の身近なエコな活動のひとつだ。
コロナ禍の2020年7月にはレジ袋が有料化され、2021年には日本政府も「カーボンニュートラル」を2050年までに達成することを国際公約として掲げた。スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥーンベリさんのようなZ世代(1990年代後半から2010年代前半に生まれた若者)は環境問題を自分事として捉える向きもあり、たかがガムといえども、かみ終えたガムをどうするかという問題は、生活者の心理に陰を落としている。