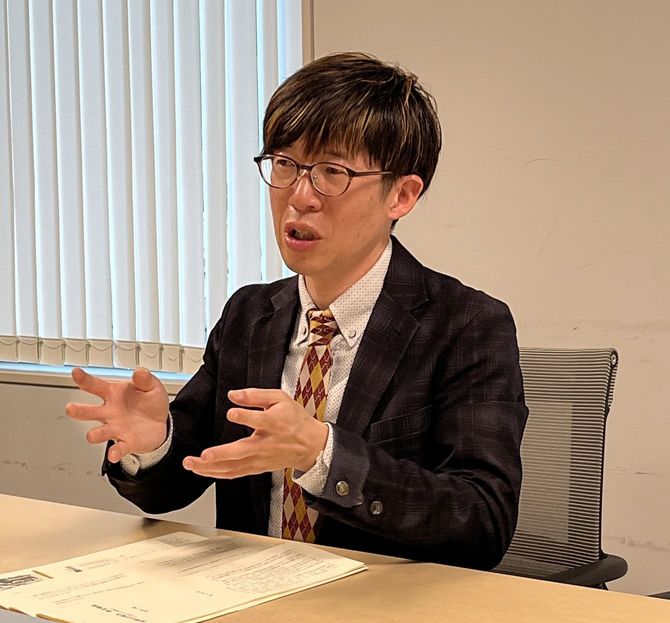「首都・南京」を落とせば終わると思っていたが…
――「ダラダラしている」は後期日中戦争の特色ですね。日本軍も蒋介石も毛沢東も、プレイヤーの全員があまり真剣じゃない感じがあります。この時期、日本は何を目指して戦い、この戦争をどう終わらせようと考えていたのでしょうか。
落としどころがなかったのでしょう。何のための戦争なのかも、もはや誰もがよくわかっていなかったと思います。東亜新秩序や大東亜共栄圏といったスローガンは、あくまでも後付けのもの。いわゆる「暴支膺懲」(横暴な中国を懲らしめよ)という懲罰感情も動機でしょうが、「懲らしめる」の定義が明確ではないので、やはり答えがない。「蒋介石の首を取る」ことも、奥地に逃げてしまったので不可能ですから。
――日本軍も、最初からそんな戦いをするつもりはなかったはずでしょう。
本来、首都の南京を落とせば3〜4カ月で終わると思っていたはずです。むかしの『ファミコンウォーズ』というゲームみたいに、敵の首都を制圧すれば終わりと。1937年の夏から秋にかけて、蒋介石の地盤でもある上海では国民党軍の中央軍と日本軍の激戦がありましたが、その裏では停戦交渉がおこなわれていました。
ただ、当時の日本は満洲国の承認や賠償金の支払いといった過大な要求を行いました。ゆえに中国側が答えを渋ると、日本側は「国民政府を対手とせず」、つまりお前たちは交渉相手にしないとさらに強気に出た。こうなると停戦交渉はできません。
――日本が悪いカードを切りすぎていますね。
そうなんです。また、南京を陥落させても、蒋介石が首都を内陸部に移転させていますから、「首都を制圧して勝ち」になりません。蒋介石も別に日本と戦争をしたくはないのですが、弱腰になると対立する共産主義勢力から批判を受ける。引けない泥沼です。
中国軍が驚いた「日本軍の意味不明な行動」
――中国の戦争は、基本的には『孫子』が意識されるはずです。戦略目的を達成するために武力を用いず勝つのが上策で、戦争をする場合も短期決戦。長期戦はお金もかかりますし、割に合いません。そんな中国人から見て、日本軍の行動は意味不明だったのではないでしょうか。
そう思います。毛沢東は『孫子』を読んでいたでしょうし、蒋介石も意識していたでしょう。なので、軍を引いて引いてのゲリラ戦に持ち込んだ。特に八路軍(中国共産党の軍隊、人民解放軍の前身)はそうです。日本軍は敵を叩いても叩いてもきりがなく、疲れたら反撃される。毛沢東の術中にはまっているわけです。
そもそも日本軍は、個々の戦闘に対する戦術はありますが、戦略はない。ゲリラが出たから毒ガスや細菌を撒く、八路軍の根拠地に対する三光作戦(殺し尽くし・焼き尽くし・奪い尽くす)のような行動をやってみる……と、対症療法的にはいろいろやるのですが、眼の前の課題にモグラ叩きのように向き合っていただけです。そうなると、最終的には戦略を持っているほうが、「敵を撤退させる」という形で勝つことになります。