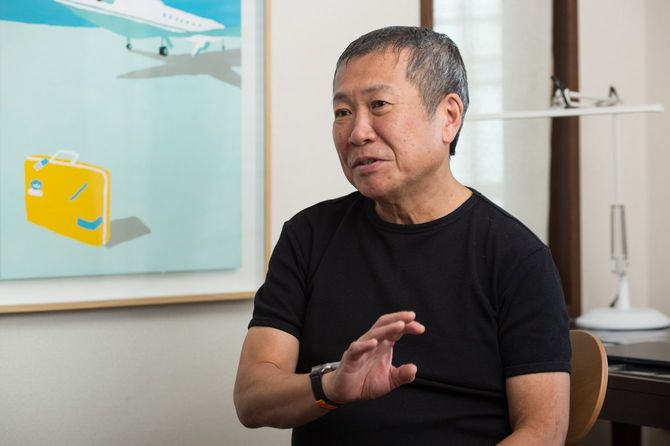※本稿は、佐々木俊尚『この国を蝕む「神話」解体』(徳間書店)の一部を再編集したものです。
マスコミの「弱者に寄り添う」の「弱者」とは誰か
「弱者」「マイノリティ」などの用語は、21世紀になって棍棒のように振り回されすぎたせいで、すっかり軽いことばになってしまった。新聞やテレビ、ツイッターなどいたるところに「いまの政治にはマイノリティへのまなざしが欠落している」「弱者に寄り添え」などの言いまわしがあふれている。
もちろん、弱者の味方をすることが悪いわけではない。弱者を救うのは当然のことだし、それを否定する人はいないだろう。では、このように「弱者」「弱者」と言いつのることの問題点とは何か。
それは「弱者」「マイノリティ」がいったいだれを指しているのか、ということが大きく変化してきていると認識されていないことである。弱者の意味が変わってきているのに、それを看過してしまって、ステレオタイプに弱者、マイノリティと言い続けていることが問題なのである。
昔は障がい者やLGBTが「弱者」と捉えられていた
この数十年の歴史を振り返ってみよう。
1960年代の高度経済成長の頃から1990年代ぐらいまでは、日本は「総中流社会」と呼ばれていた。貧困はほぼ撲滅したと思われていて、格差はあってもさほどは目立たず、大半の日本人が「自分は中流である」と考えていた。マジョリティとマイノリティの違いは明快だった。
この時代のマスコミには「標準家庭」という用語があって、会社員の夫と専業主婦の妻、子ども2人の4人家族の意味だった。増税などのニュースがあると、新聞やテレビは「標準家庭では、平均して年に1万2000円の負担増になります」と解説していた。
すなわち、この4人家族こそが「標準」でありマジョリティだったのである。そしてこの「標準」に当てはまらない人が、マイノリティ。障がい者や病人やLGBTや在日の人、さらには働く独身女性なども、時にこのマイノリティの箱に入れられていた。
わたしは1990年代には、事件・事故や社会問題を扱う全国紙の記者だった。先輩や上司からは、さかんに新聞記者の理念を叩き込まれた。このような理念だ。
「マイノリティの目線で社会を見よ。社会の外側から社会の内側を見て、光を逆照射することによって、総中流社会に潜んでいる問題が見えてくるのだ」
この理念は、21世紀になっても綿々とマスコミの中に引き継がれているように感じる。しかし世紀が変わって、時代の空気も大きく変化している。それにマスコミの人たちは気づいていない。