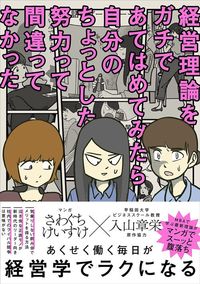地味にコツコツやる人こそが、職場の常識を変える
でも、既存の常識は周囲が思い込んでいる幻想ですから、それを変えていくのは、そもそもとても困難なのです。みなさんのなかにも、職場の何かの常識を変えようとして周りの賛同が得られず、「なぜみんなは変わろうとしないの⁉」とイライラした経験がある方もいるかもしれません。でもそれは周囲からしたら、「長年やっていることだから」「みんなやっていることだから」という当たり前すぎる常識なので、変えるという発想がないわけです。
どうやったら、この常識を変えられるのでしょうか。もちろん社長であればやりやすいわけですが、みなさんの多くは社長ではありません。そこで大事なのは、単純ではありますが、「とにかくコツコツと変革活動を続けて、次第に仲間を巻き込み、ムーブメントをつくっていくこと」です。ムーブメントも、経営学の研究範囲なのです。
実際、「変革に重要なのは、スーパーヒーローではなく、日々の地道な行動の積み重ねである」という研究結果が示されているんですよ。
僕の周りでそれを実現した代表格の1つは、元パナソニック社員の濱松誠さんが起こしたムーブメントです。「組織の壁を乗り越え、パナソニックをよくしたい」という思いから、濱松さんは2012年に会社横断の有志の会「One Panasonic」を設立しました。さまざまなイベントを開くうち、活動はやがて経営層を巻き込んだものにまでなりました。さらに今度は、他の大企業の同世代と2016年に、大企業の若手をつなぐ「One Japan」を発足。One Japanはいまや大きなムーブメントになっています。
社会レベルでムーブメントをつくってきたのが、病児保育事業を手掛ける認定NPO法人フローレンス代表の駒崎弘樹さん。駒崎さんは内閣府の「子ども・子育て会議」に委員として参加するなど、政策提言活動を地道に展開。政治家とも密に交流します。その結果、小規模認可保育所が国の認可事業となるきっかけをつくりました。地道な行動により、「子どもの預け先がないから働けない」という母親たちの世界の常識を、見事に壊したわけですね。
楽しくやることが何よりも大事
もう一点、このような活動での僕からのオススメは、「とにかく楽しくやること」です。楽しくやるのはとても大事です。
歯を食いしばり、血まなこになって「常識は幻想です!」と叫んでも人は近寄ってきません。楽しく続けていれば、「なんだか面白そうなことをしているな」と気になった周りの人たちが、自然に集まります。賛同者の輪が広がってくると、やがてどこかのタイミングで潮目が変わるときが来ます。そして最初は反対していた人も、「実は私もずっと同じことを考えてたんだよ」などと言い出したりするのです(笑)。
これまでの世の中も、コツコツと変革を続けた人がやがて多くの人を巻き込んで、変革のムーブメントを生んできました。社会変革のような大きなものでなくても、まずはみなさんの職場の周りなどで、変な常識をコツコツと変えてみてください。