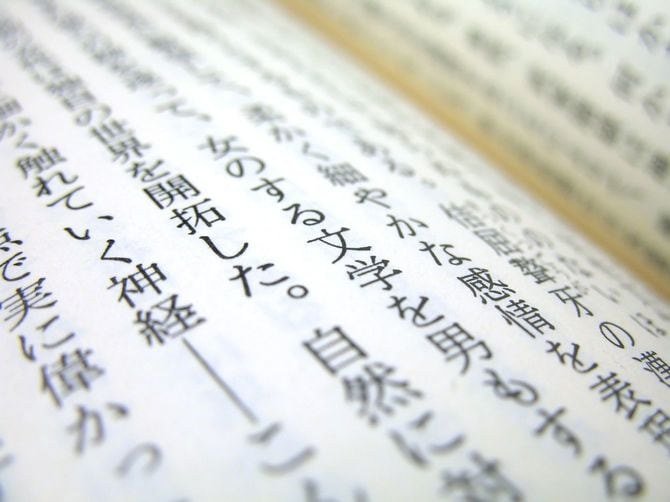幼い時の「熱中力」が考える力を身に付ける
幼い子供は好奇心の塊だ。例えば恐竜が好きな子なら、何時間でも夢中になって図鑑を眺めていられる。せっかく本を読むのなら、もっと勉強に役立ちそうな本を読めばいいのに、と親は思ってしまいがちだが、ここはそっと見守ってあげてほしい。なぜなら、この熱中している時間こそ、子供の頭の中は「なぜそうなるのだろう?」「だったらどうなるのだろう?」と思考を巡らせているからだ。
何に夢中になってもいい。
「このお魚と前に見たあのお魚は形が似ているなー。でも、違う名前なんだな。どこが違うのだろう?」
「積み木を高く積み上げるにはどうしたらいいんだろう? こっちに乗せたらグラグラしないかな? それともこっちかな?」
そうやって、興味の赴くままに、物の類似性や相違点を確かめたり、原因を探り因果関係を発見したり、創意工夫したりしているうちに、無意識に頭をフル回転させているのだ。こうした経験の積み重ねが、「思考力」を育てていく。また、自分で考えて解決方法を見つけられたという経験をした子は、「まずはやってみよう。きっと何かいいアイデアが浮かぶはずだ」と粘り強く向き合えるようになる。こうした姿勢こそが、今の理科入試を解くときに求められる姿なのだ。
勉強だけやらされた子は他者の気持ちが理解できない
国語入試にも変化が出ている。
ひとつは、理科と同じように長い出題文(物語文・説明文)を出す学校が増えている。例えば、都内では麻布、駒場東邦、海城、神奈川では浅野、聖光学院といった学校は試験時間50~60分の中で8000~1万字近い出題文を出し、解答は選択式ではなく、記述式にするケースも目立つ(参考文献「中学受験ろぐ」)。読むスピードや表現力も問われる。傍線前後を読み返してテクニカルに解く力だけではなく、読み通して全体を俯瞰することを求められている。「結局、この作者は何を言いたいのか」という問いに答える力がより大切になってきたことになる。
「物語文」にも大きな変化がある。物語文といえば、かつては同じ年頃の子供が主人公の物語を取り上げるのが主流だった。そのため、友達にこう言われたから悲しくなったとか、もしお父さんとお母さんと離ればなれに暮らすようになったら寂しいなとか、自分と重ねて考えたり、想像したりすることができ、主人公の気持ちやとった行動を理解したり、共感したりすることができた。
ところが最近の中学受験の国語入試では、同世代の子供が主人公の物語は減少傾向にあり、小学生の子供が知らない時代背景の話だったり、主人公が同じ年頃の子供ではなく大人の物語だったりと、小学生の子供が理解するには難しい内容の話が取り上げられる。男子校の入試で仕事と子育ての狭間で悩むお母さんの葛藤を聞いてきたり、同じ年頃の女の子の恋心を聞いてきたりといった具合だ。
こうした問題を前にしたときに、「僕は男だから分からない」「経験したことがないから知らない」では、解き進めていくことはできない。
では、なぜ小学生にこのような長くて難解な問題を出すのか?