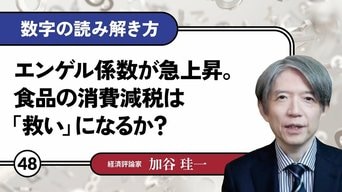古典派経済学の通念をことごとく破壊した

ケネディはハーバード大の教え子。政権発足時は要職を期待されたが、「インドの歴史や文化に感銘を受けた」と駐印大使を務めた。
バブルだろうと景気変動だろうと、我々は未来を見通す力を持たず、予測を可能とするような確固とした道しるべも持ち合わせていない。我々の生きているこのような時代を、ガルブレイスは「不確実性の時代」と呼んだ。これは監修を務めた英BBCの連続番組のタイトルとなり、その後、本にまとめられ、世界的なベストセラーになった。
アダム・スミスから、リカード、マルクス、レーニン、そしてケインズへと至る経済思想史をたどりながら、「確実と思われた経済思想」がなぜ規範性を失ったのか、その歴史的背景を明るみに出そうとしたのが『不確実性の時代』である。
彼の著作は平明、平易、現代の経済を解き明かそうとする場合にもグラフや数式は用いず、「ゆたかな社会」や「新しい産業国家」のイメージを言葉の力によって描き出そうとする。彼は経済学者というより経済批評家と見なされてきたが、言葉の力は時として数学の力にまさる。彼の友人であったサミュエルソンは、「私たちノーベル賞受賞者の大半が図書館のほこりをかぶった書棚の奥の脚注に葬り去られる時代になっても、ケン・ガルブレイスは(中略)忘れ去られることもなく読まれ続けるだろう」(リチャード・パーカー『ガルブレイス』)と述べている。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント
(構成=プレジデント編集部)