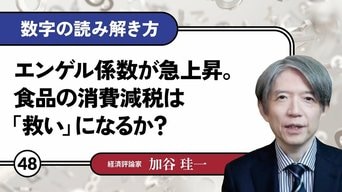※本稿は、戸高一成・大木毅『帝国軍人 公文書、私文書、オーラルヒストリーからみる』(角川新書)の一部を再編集したものです。
広く人材を集めて育てる「予科練」制度の光と影
【戸髙】第一線で戦った者の大多数は下士官兵です。特にもっとも危ないと思われたのが、飛行機乗りです。
昭和初期、飛行機がだんだん重要性を増すと、問題が起きました。パイロットの絶対数が足りなくなったのです。ヨーロッパでは習慣的にパイロットは士官です。なぜかというと、飛行機は一度空に上がると、パイロットが一国一城の主で、一人ひとりが戦闘の判断をしなければいけません。原則的に士官でないと、戦闘判断は行わないからです。
【大木】しかも、貴族出身者が多いですね。
【戸髙】そうです。日本では階級による制限はありませんでした。日本の場合は、適性のある若者を鍛えたらよかろう、将来は士官的な扱いをしようと、昭和四(一九二九)年から予科練という制度を始めます。
最初は高等小学校卒程度、現代の中学生ぐらいの練習生を募ります。ところが、まだ足りない。そこで「マル3計画」(正式名称は第三次海軍軍備補充計画。大日本帝国海軍の海軍軍備計画のこと)によって増員をします。それでも、まだ足りない。今度は、一般教養を教える時間を省いて、すぐにパイロット教育をしたいという理由から、昭和一二(一九三七)年に募る練習生の年齢を引き上げます。現代でいうと高卒ぐらい、少し年上の練習生です。
その練習生に付けられた名前が、後々まで問題を引きずります。海軍は本当にネーミングのセンスがありません。中学校卒の練習生には「甲」、高等小学校卒には「乙」、水兵出身者には「丙」、つまり甲乙丙という、まるで成績順のような名前を付けたのです。例えば、乙飛(乙種飛行予科練習生)は、自分たちのほうが兵士としてははるかに先輩なのに、甲飛(甲種飛行予科練習生)の名が上に書かれます。それが不愉快で、年中摩擦が起きました。