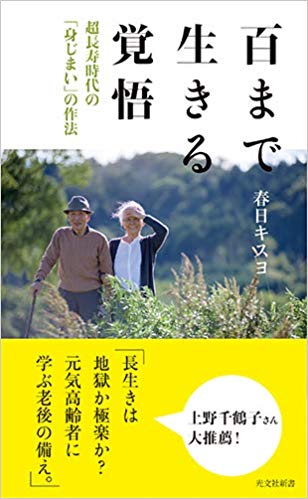「近親者がするのはあたりまえ」ではない
Xさんの話を聞きながら、私が「すごいなあ」と思った点がいくつかあった。
まず、「倒れた時のことなどを考えるのは暗いこと」と言う人がいるが、Xさんは明るく意欲的で、施設探しも自分で情報を探し、「自分で何もかにもせんと駄目だと思っているから」と、一人で見学に行くと言う。これはこの年代の女性では珍しいことである。
さらに、甥に保証人など重要な事項を依頼しているが、必ず、姉、甥、甥の妻の3人同席の場で話を進めるのだという。
Xさん「そういう話の時は、姉と甥夫婦、3人一緒の時にするんです。3人が納得してくれないと、何かする時絶対うまくいきませんからね。葬儀の件についても4人で一緒に葬儀社に行って、前金を払って契約してきました」
さらに、何か上記のような取り決めをして、それを行ってもらった場合、必ず相応の金銭授受がなされていることである。それもきちんと「ありがとう」と感謝の意を伝え、その金額を支払う理由を口頭で説明し、お金を手渡すという。
一見、こうしたことは易しいように見えて、「近親者がするのがあたりまえ」とする金銭感覚の場合、案外難しいことかもしれないと思ったのである。
親族と離れて暮らしても「死に支度」が完璧
Xさんには「死に支度」「老い支度」を手伝ってくれる甥夫婦や姪、姉といった身近な親族がいた。それにXさんはまだ、80歳。自分でこれから入りたい施設見学をする足腰の達者さも残っていた。しかし、Yさんは、5人姉妹の末っ子で、存命の姉2人(96歳、93歳)はすでにケア施設に入所し、甥や姪も他県に居住し、頼れる身近な親族がいない。しかも、Xさんよりも10歳年長であるYさんは、変形性股関節症もあって、年々痛みが増し、歩行が不自由になっていた。かといって、Yさんの暮らしは孤立したものではなく、彼女自身が手紙や電話で関係を丁寧に育んできた「他人」とのつながりの中で、「これからもここで、在宅で暮らしたい」と穏やかな日々を過ごしている。
Yさんが70代から取り組み始めた「老い支度」「死に支度」には、いくつかのことがあった。一つは、ひとり暮らしの自分が自力で生活できなくなった時に、世話を託すケア施設を探すこと。さらに、亡き母親が自分に託した墓じまいと先祖の永代供養をお寺さんにしてもらうこと。それに、自分が死んだ後に財産が残った場合の贈与先を書いた遺言書を書くこと。そして何より、自分が倒れた時の保証人になってくれる先を確保すること。