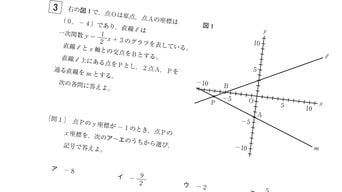2005年から大きく変わった

後藤晃・政策研究大学院大学教授
市場経済の基本ルールを定めた独占禁止法だが、企業から見ると「公正取引委員会は敵」と映るように、法律の趣旨がなかなか理解されない面がある。
経済のグローバル化が奔流のように進み、イノベーションを促進する競争政策の導入が喫緊の課題となる今日、独禁法を軽んじていては経営に支障をきたすばかりか、日本経済に悪影響を及ぼす可能性が出てくる。
そこで、独禁法に詳しい後藤晃・政策研究大学院大学教授に、主に経済のグローバル化とイノベーションの促進に焦点を絞り、法律の運用や最近の動向についてアカデミズムの立場から解説してもらった。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告非表示で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント