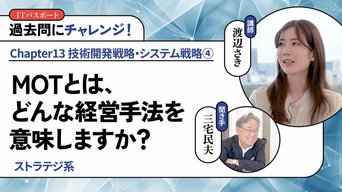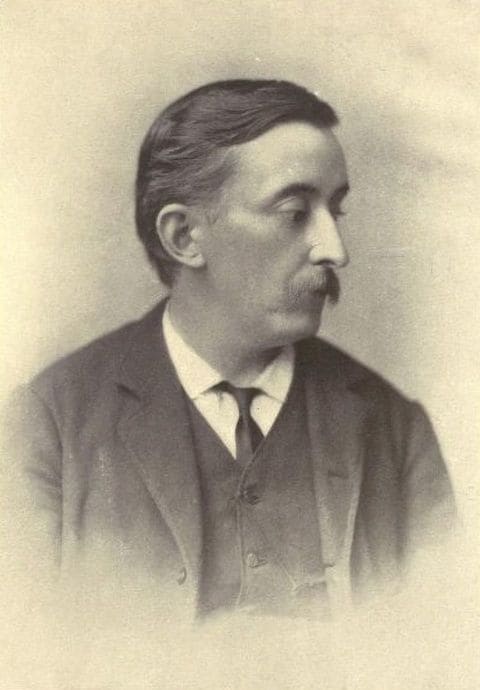
女中“代わり”の「お信」との交流
NHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」では、県知事の娘・リヨ(北香那)がヘブン(トミー・バストウ)に猛烈なアタックを仕掛け続けている。ヘブンのモデルとなったラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が、実際に県知事の娘から激しく求愛されていたのは事実だ。
だが――。
史実の八雲には、ドラマでは決して触れられない「もう一人の決定的な女性」が存在していた。しかも、その関係はセツとの結婚をも左右したほど深く、そして複雑なものだった。
それが、八雲が最初に滞在した冨田旅館の女中、お信である。「ばけばけ」では花田旅館の女中・ウメ(野内まる)として描かれているが、ドラマが決して踏み込まないであろう、八雲とこの少女との濃密な関係がそこにはあった。
八雲が滞在していた冨田旅館の主人・冨田太平とツネ夫婦が昭和になって取材を受けた「冨田旅館ニ於ケル小泉八雲先生」という記録が残っている。以前の記事でも触れた資料だ。
この証言によれば、当時旅館には夫婦のほか、「懇意先の娘で女中代わり」のお信と2人の召使いがいたという。
「女中代わり」とは妙な表現である。
実際、八雲が毎日たしなむ煙管の世話はたいていお信がやっていたと夫婦は語っており、彼女が女中の仕事をしていたのは間違いない。では、なぜわざわざ「代わり」などという言い方をするのか。
#ばけばけオフショット
— 朝ドラ「ばけばけ」公式 放送中 (@asadora_bk_nhk) November 30, 2025
松江に冬が訪れました。
八雲の同僚・西田千太郎の日記にも「近年稀有ノ積雪」と記されている程、この年の松江は寒かったようです。
暖炉もストーブもない、木造の日本の家屋。
ヘブンさんには「ジゴク!」の寒さです。#髙石あかり #トミー・バストウ #野内まる#ばけばけ pic.twitter.com/m6KunFphfo
旅館の夫婦が「頼まれて仕方なく引き取った」子供
その理由は、夫婦自身の証言の中に隠されている。お信が関わるあるエピソードを語る際、夫婦はこう記しているのだ。
お信は血縁者でもないのに「頼まれて仕方なく引き取った」子供だったというのである。そして、女中代わりのお信のほかに、召使いが二人いると書かれている。つまり、正規の使用人はちゃんと雇っていた。にもかかわらず、お信だけが「女中代わり」なのだ。
この言葉の裏には、冷酷な現実が透けて見える。正式な女中には賃金を払う。だが、「頼まれて仕方なく引き取った」お信には払わない、あるいは雀の涙ほどしか渡さない。そういう区別である。
血縁もなく、頼る者もいない。「仕方なく」引き取ってやったのだから、働いて当然……冨田夫婦の証言からは、そんな傲慢さすら漂ってくる。要するに、身寄りのない子供を善意の仮面の下で、実質的に無償の労働力として使っていたということだ。
もちろん、明治期の家制度においては、奉公や“引き取り”がそのまま労働と結びつくのは一般的な慣行だった。現代的な児童労働の概念をそのまま当てはめることはできない。とはいえ、史料からはどこかやりきれない想いを感じてしまう。