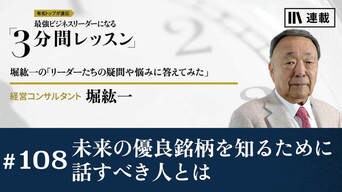2020年の改正健康増進法の施行により、屋内の原則禁煙が義務付けられた。「分煙」といいながら、世間は「禁煙」を求めているように感じる毎日だ。安心してたばこが吸える場所だった喫煙所も日に日に減っていく。
今年3月、東海道、山陽、九州新幹線の車内に設けられた喫煙ルームが廃止されて全面禁煙となった。JR東日本の管轄の新幹線ではすでに全面禁煙だから、日本中の新幹線で、完全にたばこが吸えなくなってしまった。だが、旧国鉄の債務は、1本につき約1円の「たばこ特別税」で返済している。旧国鉄の債務を返済している愛煙家に対して、JRの仕打ちはひどいと思う。
紙巻たばこ1箱580円のうち約6割が税金だ。JTの発表によると、内訳は国たばこ税が136.04円、地方たばこ税が152.44円、たばこ特別税が16.40円、消費税が52.72円。これらのたばこ税全体の税収は年間2兆円にのぼる。2兆円という金額は、消費税収の1%分相当だ。ちなみに、ビールの税率が約4割、ウイスキーの税率が2〜3割だから、われわれ愛煙家がどれほど国や地方に貢献しているかをもっと多くの人に知ってもらいたいものだ。最近、ある経済学者が「たばこを吸う人がゼロになったら、2兆円の税収がなくなり、消費税を1%上げることになる」と話している記事を読んだ。国民の大多数から「消費税率が上がってもいいから全国民が禁煙」という声が上がるのであれば、私も禁煙にチャレンジしてみてもよいが、おそらく、消費税率を上げないことを選ぶ人がほとんどだろう。
この莫大な税収があるから、東京都をはじめ、独自の禁煙条例を定めている自治体でも、たばこ販売を禁止していないのだと思う。本気ですべての国民に禁煙させたいなら、売らなければいいだけの話である。
日本の状態は中途半端
以前、厚生労働省が発表した「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」について触れた。これは飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を推進するため、飲酒による身体への影響や疾病・行動に関するリスクなどを伝えるとともに、健康に配慮した飲酒の仕方や量についてまとめたものだ。
このガイドラインでは、生活習慣病のリスクが高まる1日の飲酒量は男性が40グラム以上、女性は20グラム以上とされている。これはあくまでもガイドラインで罰則などはないが、国民の酒量が減少すれば、単に酒造メーカーだけではなく、飲食店やその周辺産業で働く人にとっても、ダメージは大きいうえ、他産業にこの流れが波及すれば、多くの嗜好品が消滅しかねない。嗜好品の選択に国が口出しをするためには、慎重な議論が必要だと思っている。
ちなみにイギリスでは今年4月に、2009年以降に生まれた人は生涯にわたってたばこを買えないという法案が可決された。子どもたちにたばこを販売した店舗には罰金も科される。米国では若者に人気の果物などのフレーバーつき電子たばこ「ジュール」の発売が禁止になったという過去もある。いずれも、若年層へのたばこの健康被害を防ぐとともに、将来の喫煙者を増やさないための措置だ。
実際にたばこが買えなくなれば、愛煙家もあきらめがつくだろうが、日本の状態は中途半端だ。「健康のため禁煙推進」といいながら、「税収のため、たばこは地元で買ってください」という。勘弁してほしい。