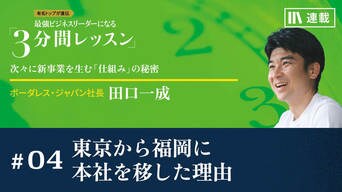休養の組み合わせで疲労回復効果UP
ここまで7つのタイプの休養法をご紹介しましたが、次に、それらの休養法を、どのように組み合わせればいいのかをご説明しましょう。
複数のタイプの休養をセットで行えれば、疲労回復効果の倍増も期待できるでしょう。
実は、一つの休養法が、複数のモデルに当てはまるケースも少なくありません。
例えば、フィットネスジムに定期的に通っているビジネスパーソンであれば、ほかの常連客と親しくなることはありませんか?
ジムでウエートトレーニングをしたり、水泳をしたりするのは、もちろん運動タイプの休養ですが、「ジム友」とも会話が弾むようになれば、親交タイプの休養も、同時にできるわけです。
日常生活を振り返ってみると、私たちは、休養に役立ちそうなたくさんの活動を、何気なくこなしていることがわかります。
例えば、私のケースですが、休日の昼間、自宅の庭の掃除や草むしりをした後、縁側で寝転んで「日向ぼっこ」をしたり、家族と近況について話をしたり、愛犬と遊んだり、読書をしたり、外の景色を眺めてあれこれ空想したりするのが、日課になっています。つまり、休日の昼間には、転換タイプや運動タイプ、休息タイプ、親交タイプ、造形・想像タイプといった、さまざまなタイプの休養を実践しているわけです。
重要なのは、「日常のルーティンも休養になる」ことを理解したうえで、そうした活動を、できるだけセットで行えるように意識すること。そうすれば、効率的に疲労が回復できるようになるでしょう。
疲労と休養のマネジメントに取り組む
疲れ方も、休み方も個人差があるので、例えば、「どのくらいの仕事量だと、どのくらい疲れるのか」、さらには「疲労度によって、パフォーマンスがどのくらい下がるのか」が「見える化」できれば、「どのくらい休養すれば、パフォーマンスが回復するのか」ということも、把握できるようになるでしょう。
手始めに、自分の「疲労感のレコーディング」をしてみましょう。毎朝の疲労感の度合いを、「○△×」の3段階といった、簡単なメモでもいいので、記録していくのです。同時に、簡単な活動内容も記録しておけば、仕事の負荷に応じた疲労度との関係も、わかるようになります。パフォーマンスの向上にも役立つので、ぜひお試しください。
※本稿は、雑誌『プレジデント』(2024年6月14日号)の一部を再編集したものです。