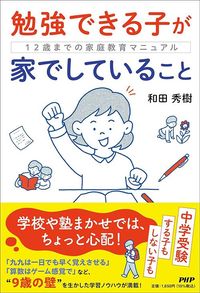獲得目標をはっきりとさせて勉強させる
子どもから、「大人になって、理科なんか役に立つの?」「難しい算数なんて大人になったら使わないんじゃないの?」などと問いつめられて、困ってしまったという経験を持っているお父さん、お母さんもいるかもしれません。
こういう場合には、獲得目標を明確にして子どもに勉強をさせることが必要になります。
個別の教科については答えに詰まる場合もあると思いますが、勉強が「社会に出てから役に立つ」ということだけは間違いありませんので、そこをきちんと伝えるべきなのです。
受験の際に志望校を設定し、それに何とか合格するような方策を工夫することは、そのまま社会に出て役に立つことばかりです。
また、「勉強をする習慣を身につけること」「努力を維持し続けること」「自分の感情をコントロールしながら、スランプであっても努力し続けることができるようにすること」なども、社会に出てから役に立ちます。
同様に、「わからないことがあれば人に聞く」ということも社会に出てからの重要な要素になります。
受験学力をつけるという行為自体から、非常に多くの社会的能力を獲得できるのだということをきちんと子どもに教えてあげましょう。
勉強することで、社会人として必要な、どんな能力を獲得すべきなのかという「獲得目標」さえはっきりさせてあげれば、子どもも自分の態度を前向きに変えることができるようになるでしょう。
難しい課題を上手にクリアできた人ほど「仕事ができる人」と言われる
勉強というのは、楽なことばかりではありません。むしろ、苦しいのが当たり前です。だからこそ、多くの人が苦に感じないように訓練を重ねているのです。
あるいは、できるだけ苦にならないような勉強法を自分なりに工夫している人もいます。
そういうところに勉強の1つの意味があるのだと思います。
大人になってからも、苦しい課題、厳しいノルマなどを突きつけられますが、それから逃れるわけにはいきません。
そんなときに、何とか少しでも楽に切り抜けられるような方法を工夫しながら、大半の人はその課題をクリアしていきます。
そして難しい課題を上手にクリアできた人ほど、その後に偉くなっていったり、「仕事ができる人」と言われたりして、楽しく充実した生活を送ることができています。
ですから、苦しいけれども、それを何とか工夫してこなしていけば、必ず大人になってから役に立つのだということを諭してみることも必要だと思います。