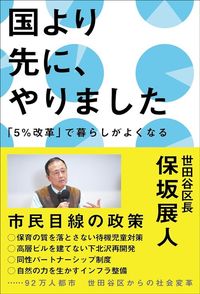計画から5年かけて話し合い、建設開始にこぎつけた
そこで、何度も説明会を重ね、地域の声を聞きながら、なんとか理解を広げていきました。「子どもの声は単なる『騒音』なのか?」と問いかけ、ワークショップも何度も開催。中には計画が開始してから建設が始まるまで、話し合いを続けて5年かかった地域もあります。
それでも、反対運動を前に事業者が撤退してしまったケースはあったものの、区として断念はしませんでした。2015年には「子ども・子育て応援都市」を宣言。子どもはすべての人にとって地域の宝である、そんなまちを世田谷区は目指しましょうと打ち出したのです。
結局、2013年には65園だった私立認可保育園が、2023年には203園まで増えました。出生数減少の影響もありますが、「ワースト」と言われた待機児童数を、2020年にゼロにすることができたのです。
定員割れで経営が苦しくなる保育園も出ている
ただ、大型マンションが建ったエリアがあったりと、地域や年齢による保育需要の偏りが大きくなったことで、2023年度は10人の待機児童がいます。さらに今年度は前年度より待機児童は厳しい状況です。また、保育園が充足してきたことで、年齢によっては希望する園児が入れてなお定員割れして経営が苦しいという保育園、地域も出てきており、今後の課題だと考えているところです。
ここ数年は、保育士の人数も必要な「ゼロ歳児枠」が4月段階で定員割れとなっています。しかし、年度途中に入園が進み、後半にはほぼ定員が埋まってきます。すると、生まれ月によって、ゼロ歳の入園枠がどこにもないという事態も起きてきます。保育利用者をカウントして、空きが出ると事業者の持ち出しになる制度ではなく、保育事業者への定額払いによる支援や、通年入園可能な制度に国が変えていく必要があります。
一方で、2023年に認可外保育所でゼロ歳児の痛ましい死亡事故が起きました。区として年に1度行ってきた立入調査を、抜き打ち検査も含めて、強化していく必要があります。区では、第三者の有識者を交えた検証委員会による事故分析と対策について提案をいただく予定です。ベビーホテルなどの認可外保育所の子どもたちの安全を確保していかなくてはなりません。