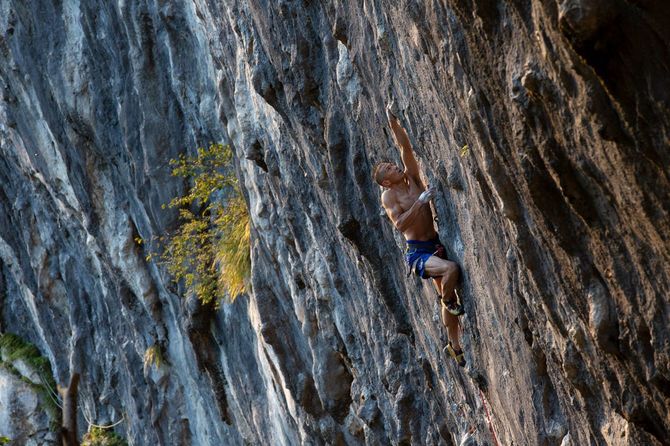日本に戻った後、3週間は放心状態だった
だからこそ、サラテを登り切ったとき、平山はこれまでに感じたことのない充足感を胸に抱いていた。2日間にわたるクライミングで日はすっかり落ち、空には数えきれないほどの数の星が瞬いていた。「登ること」と「生きること」が、今では彼の中で分かち難く結びついていた。
「次に挑戦したときは、もっとすごいスタイルで登れるはずだ」
と、平山は収まり切らない興奮の中で思った。
「そのときに感じていた心境は、クライミングを始める前の自分には全く想像もつかない境地でした。十分に分かっていると思っていたはずのものが、まだ何も分かっていなかったのだと知った。もっと先があったんだ、って。『限界』を規定しているのは自分自身なんだ、という思いが湧いてきましたよね。日本に戻った後は放心状態になって、3週間くらいは家の天井を眺めているような日々を送りました。まるでしばらくは天国にいるような心地でした」
平山にとってサラテでのオンサイトトライの試みは、「クライミング」という自らが人生をかけて続けてきたものの意味合いを変えた。その後、前述のように彼はワールドカップで二度の優勝を果たすが、あの一瞬で感じた強烈な感覚や境地は、後にも先にもそのときだけだった、という。
「死力を尽くす」とはどのようなことか
「いろんな苦労もあったし、喜びの瞬間もあった。サラテの頂上には、自分がなぜあの場所を登りたいと思ったのか、という問いの答えがあったといまでも思っています。
僕はあのワンムーブによって、死力の尽くし方、というようなものを知った。『なぜクライミングをするのか分からない』という心境の中では、死力は尽くせない。何のために自分は登るのか。その理由が明確なとき、人は死力を尽くすことができる。
クライミング自体へのモチベーションはそこから深まりました。それは僕にとって、人生をどう生きるか、という問いとつながっています。力を出し切って生きるためには、『意味』を自分の中に作り出さなければならない。僕はサラテでそのことを学んだんです」
平山がサラテでの挑戦で得たもの――。
それは「死力を尽くすとはどのようなことか」を、壁での死闘によって得た実感としての理解だった。極地を目指すという行為のためには、「生きる意味」を自分の裡に作り上げなければならない。平山のサラテでの体験は、そのことを確かに伝えている。