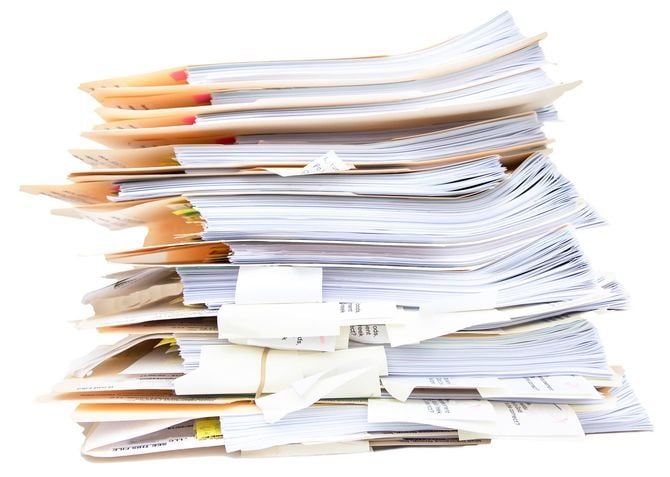ルールに縛られない自由な国際学校を目指す
校長になるための県知事との面接試験では、まずは、「自分は最も不登校の生徒が多い学校に行きたい」と話しました。または、自分の言語能力、多文化対応力、さまざまな職歴などの多様性を生かして「国際的なリーダーを育成する学校」を目指し、最終的に「茨城県初の公立国際学校をつくりたい」とも言いました。その結果、2022年から茨城県立土浦第一高校・付属中学校の副校長を、23年からは校長を務めています。
私の夢として目指す公立国際学校とは、単なる国際バカロレア(IB)やケンブリッジ方式などの教育プログラムを導入した欧米式のインターナショナルスクールではなく、日本の文化背景や東洋哲学を生かして、多言語能力育成などとともに、世界に通用する生徒を育てる教育スタイルを持つ学校です。生徒の半分は日本人、半分は外国にルーツのある子どもが理想です。
インドの学校が理想的というつもりはありませんが、インドの学校にはルールに縛り付けるということはなく、自由な発想や行動が可能であり、さらに、社会でのサバイバル能力を養成する要素が多くあると感じています。学校ではインド神話や歴史のラーマーヤナやマハーバーラタなどが、しっかりと教えられており、そこには社会を生き抜くための知恵と道徳がたくさん織り込まれているのです。
日本の教育現場はアナログまみれ
私が学校に赴任してまず感じたのは、「日本の教育現場はITシステムの導入があまりにも遅れている」ということです。日本の学校は、すべてが紙の記録で管理されており、これまでに蓄積された生徒の情報の分析や整理・共有が全くできていません。
現状では、生徒に関するデータをすぐに閲覧、利用できる仕組みが整備されておらず、校長であってもデータを見るには、別の先生に頼む必要があります。さらに、データそのものも十分にはそろっておらず、データ分析機能もありません。これでは個々の生徒に必要なきめ細かい対応はとてもできません。
生徒一人ひとりにタブレット端末を持たせるという施策も、持たせるだけで終わっており、それで何かをしようという具体的で有効な活用法がありません。ほとんどの学校で共通して2~3個のアプリを使用しています。形式だけ整えても中身がないと意味がないのです。
私の学校では、これまでは紙ベースで存在したさまざまなデータを、エクセルベースで電子化して、自分のPCで見られるようにしました。将来的にはITシステムを導入して、生徒に目標設定をしてもらい、各生徒の性格や適性、置かれた状況に合わせて、目標に向かって具体的な計画を策定させて、実行してもらいたいです。そして、その進捗をきめ細かく管理やフォローできるシステムを構築したいと考えています。ITシステム導入後は、その分析も瞬時にできるようにしたいです。
学校の変革には大きな抵抗がありますが、ITシステムを導入することで、さまざまな変革をもたらすことが可能になると考えています。