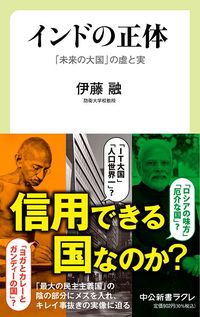「生まれ」を甘受して暮らしてきたひとびと
この問いを投げかけられたころには、私は毎日出会う、あの老人のまなざしから自分なりの答えらしきものを感じ取っていた。私が勝手に心の底で期待していたような、社会や政治に対する憤りのようなものはそこにはなかった。それはみずからの運命を受け入れつつ、そのなかで日々を精一杯生きていこうとする姿のように思われた。
ここで、カーストについてもう少し詳しく触れるべきだろう。
よく考えてみれば、インドにおけるカーストは「生まれ」であり、ひとびとは長く、みずからの置かれたその「生まれ」を甘受して暮らしてきた。それはさまざまな矛盾を抱えた巨大な国のなかで、社会を安定化させる装置として、つまり社会秩序として機能してきたのではないか。だとすれば、現代のわれわれの目線からは、議会や政府の失政、あるいは不作為に映る貧困や差別が、インドの誇る民主主義制度と共存してきたとしても不思議はない。
民主主義を「目的」として捉える傾向
長くインド政治を研究してきた広瀬崇子が指摘するように、インドでは民主主義を、生活を改善する「手段」としてとらえるよりも、それ自体を「目的」としてとらえる傾向が強かった。言い換えれば、民主主義にとって大切なのは、選挙などの手続き・制度なのであって、それさえしっかりしていれば、自由や平等が達成されたかどうかは問題にならない、という話だ。
もっとも今日では、識字率を含め、教育の進展やメディアの普及に伴って、ひとびとの意識には徐々に変化も生じている。いくつかの州においては被差別・後進カーストを基盤にした政党が台頭した。最貧困州として知られるビハール州の農村を研究した中溝和弥は、選挙によって最底辺のひとびとが政治権力を奪取する「下剋上」が起きたと論じている。インドでも、自分たちの暮らしを良くするための政治参加という考え方が広がりつつある。