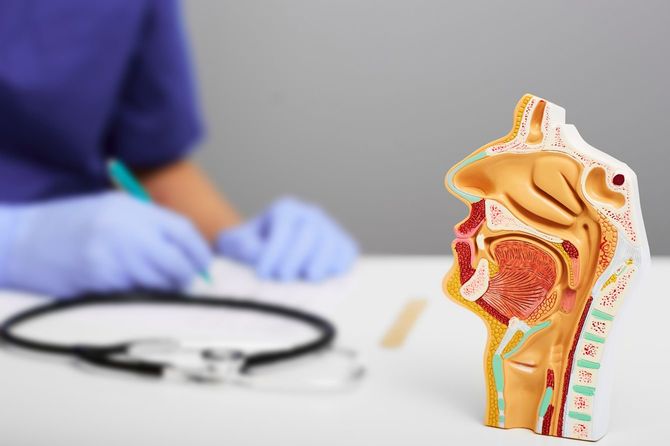ウイルスや細菌をそのまま取り込んでしまう
鼻呼吸と口呼吸との違いは、単に息が出入りする場所が違うだけではありません。鼻から取り込まれた外気と口から取り込まれた外気とでは、大きな違いがあります。
鼻の粘膜にはフィルターのような作用があり、鼻を通過することで外気中の埃やウイルスなどがある程度除去されます。また、乾燥した外気が鼻を通過することで適度に加湿されるという作用もあります。
対して口呼吸はこれらのフィルターを通らないため、ウイルスや細菌を含む外気を直接体内に取り込むことになります。これが直接的には呼吸器系の症状や、あるいは間接的にさまざまな全身症状の原因となるのです。以下にその例をいくつか挙げてみます。
・感染症にかかりやすくなる
喉の周囲には扁桃などのリンパ組織が集まっています。口呼吸では、それらが乾燥した外気に直接さらされることとなり、喉が痛くなったり、ウイルスや細菌による炎症を起こしたりするリスクが高まります。そのため風邪やインフルエンザなどにかかりやすくなります。
・虫歯や歯周病、口臭の原因に
口を開けていると、口腔内が乾燥するので、唾液が減り、口腔環境にも影響が出ます。唾液には食べかすやプラークを洗い流したり、歯の再石灰化(表面修復)を行ったりと、虫歯や歯周病を防ぐ作用があります。唾液が減ると、こうした作用が十分に働かなくなるため、虫歯や歯周病にかかりやすくなりますし、口臭の原因となってしまいます。
・アレルギーとの関係も
先ほど、喉の奥にある扁桃が炎症を起こして感染症にかかりやすくなると説明しましたが、一方で扁桃は本来、ウイルスなどの異物が体に侵入するのを防ぐ免疫の役割を担っています。
しかし、口呼吸によって扁桃が外気に直接さらされ続けると、免疫異常を引き起こすことがあります。体に侵入した異物に対して免疫が過剰に反応してしまう状態がアレルギーです。喘息にはさまざまな要因がありますが、アレルギーもその一つとされており、口呼吸だと、鼻呼吸の人よりも約2倍、喘息になりやすいという報告があります。アレルギー性鼻炎の人は、口呼吸だと約4倍喘息になりやすくなることも示されています(※)。ほかにも、口呼吸はアレルギー性鼻炎やアトピー性の皮膚炎発症の一因であるという研究があります。
・過敏性腸症候群や潰瘍性大腸炎を引き起こす可能性も
口呼吸によって、扁桃が慢性的に異物にさらされ続けることが全身の免疫低下につながり、下痢や腹痛を起こすこともあります。過敏性腸症候群や、指定難病である潰瘍性大腸炎などの原因になる可能性も示唆されています。これらの疾患は、原因ははっきりしていませんが、免疫の過剰反応が関与しているとも考えられており、口呼吸を減らすことで症状が改善したケースもあるそうです。
(※)Izuhara et al. “Mouth breathing, another risk factor for asthma: the Nagahama Study” Allergy. 2016 Jul;71(7):1031-6.