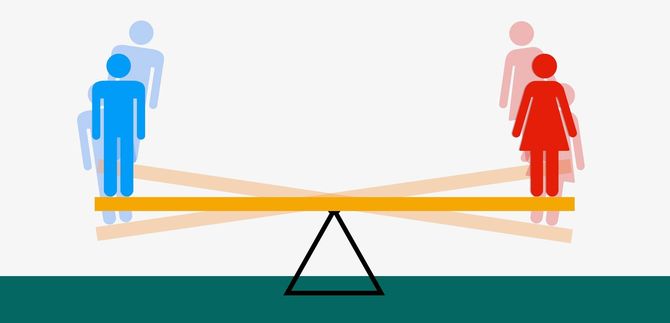ファーストキス
日本で性同一性障害という言葉が広がり始めたのは、2000年前後からだと言われている。そのきっかけとなったのは、埼玉医科大学で性同一性障害の人たちに対する性別適合手術を行うことが倫理的にも正しいと認められ、公に治療が行われるようになったことだった。
それ以前にも、アメリカでそういった動きがあることが一部では知られていたが、2000年代にテレビドラマで取り上げられるようになった影響で、日本でも徐々に広まっていった。
向坂さんが中学生だった1980年代は、まだ性同一性障害の概念がなく、向坂さん自身、女性の体である自分の中に男性性があるような違和感があったが、自分が性同一性障害だと気付くことは不可能だった。そのため、それを誰かに相談するという発想もなかった。
「鳶職やタクシードライバーをしていた私の父は、寡黙で穏やかですが、テレビにLGBT(性的少数者)の人たちが出演しているのを見ると、悪気なく『気持ち悪いな』と言ってしまうようなデリカシーに欠けるところがあり、LGBTという存在自体を全く理解ができない人です。
母は、普段は明るく話し好きで人当たりも良いのですが、一方でプライドが高く頑固で、一度怒りのスイッチが入ると暴走しやすく、一通り感情をぶちまけた後は打って変わって固く口を閉ざし、目の前にいる私はまるで存在していないかのように、母の気が済むまで無視され続けました。また、私が母の気に入らないことをしようとすると、『お前は死んだと思うことにする』と言われることもしばしばありました。だから親に相談しても、まともに相手にされないだろうと思っていましたし、自分からうまく説明できる自信もありませんでした」
親しい女友だちから、「壱ちゃんが男の子だったらよかったのに」と言われたとき、向坂さんはつい、うれしくなって母親に話してしまった。すると母親は、「私は男の子なんて産んだ覚えはない! そんなことは友だちであっても、軽はずみに言ってほしくない!」と激昂。それ以降、「母には私の性別違和について話すことはできないな」と諦めた。
中学の3年間は特に悩んだという向坂さん。一時は本気で「将来はオナベ(職業上、男装して男性のようにふるまう女性など)になろうか」と考えたこともあったというが、性別に関する悩みは、友人にも親にも、誰にも話そうとしなかった。
ただ、小学校高学年から中学3年間は、親しい友人の間でだけ、一人称を「俺」と言って男子のように振る舞い、友人たちも男子扱いしてくれていた。中学に入ってからは、演劇部に所属。文化祭で学ランを着て男子を演じることなどで、精神的に救われていた部分もあったという。
そんな中学2年の冬休み、同じクラスで比較的仲の良かった女友だちの長澤さん(仮名)から、「泊りがけで遊びにこないか」と誘われた。性別の違和感はあっても、まだ性指向についてはあまり意識していなかった向坂さんは、フラットな友だち感覚で遊びに行く。
すると就寝前、長澤さんの部屋で2人きりになると、恋愛相談を持ちかけられる。修学旅行のノリに近い恋バナかと思ったが、だんだん長澤さんが思いを寄せる相手が自分であることが分かり、やがて「キスしてほしい」とせがまれた。
「私はこのとき、一気に自分の性自認を意識してしまい、『男としてこういうときは、女の子の気持ちに応えるべきか』それとも『我慢するべきか』かなり迷いました。結局、半ば押しに負ける形でキスをしてしまいましたが、今度は性欲が湧いてきて、そのまま続きをするかしないかさらに迷いました」
まだ中学2年生の向坂さんは、続きをするにも自分には挿入するものがなく、どうしたらよいかわからなかった。さらに、中途半端に続けて、かえって悶々とするより、キスで終わらせたほうがまだ我慢ができそうだと考え、それ以上は踏みとどまった。
「その頃はまだ、同性愛に対して今ほど理解が進んでいません。長澤さんとの行為がレズビアンになると思った私は、自分がレズビアンだったのかということに対してショックを受けました。そしてファーストキスが女子だったという事実は、その後長い間、他人に知られたくない出来事のひとつになるとともに、親に申し訳ない気持ちになりました」