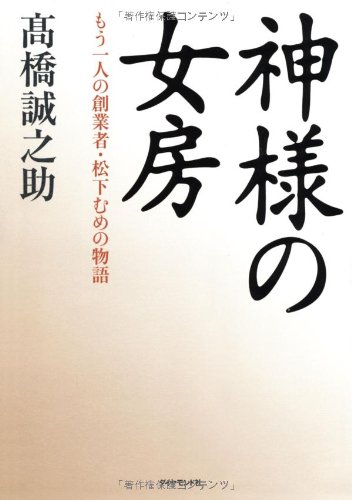高橋誠之助●たかはし・せいのすけ 1940年、京都府生まれ。63年神戸大学卒業後、松下電器産業(現パナソニック)入社。営業の第一線で活躍したのち、松下家の「執事」を20年以上務める。95年、松下社会科学振興財団支配人、2005年定年退職。
松下幸之助の妻、むめのの生涯を描いた『神様の女房』の著者は、松下家の元「執事」である。
松下電器の営業マンとしてバリバリ働いていた高橋誠之助さんが、突如、「松下家に入った」のは1969年、29歳のとき。執事として松下家のヒト・モノ・カネの「交通整理」一切合財を任されたのである。意表をつく人事だった。なぜなら、高橋さんと幸之助の接点は、社内勉強会でたった一度、質問したことがあるだけ。その内容は「これから伸びる家電量販店とどう付き合っていくべきか」というものだったという。
「それほど目にとまる質問だったとは思えません。候補は何人かいて、きっといろいろ調べられていたと思いますが、今もって、なぜ私だったのか、真相はわかりませんなあ」
以来、高橋さんは特に幸之助の妻、むめのさんと多くの時間を過ごすことになった。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント
(鈴木誠一=撮影)