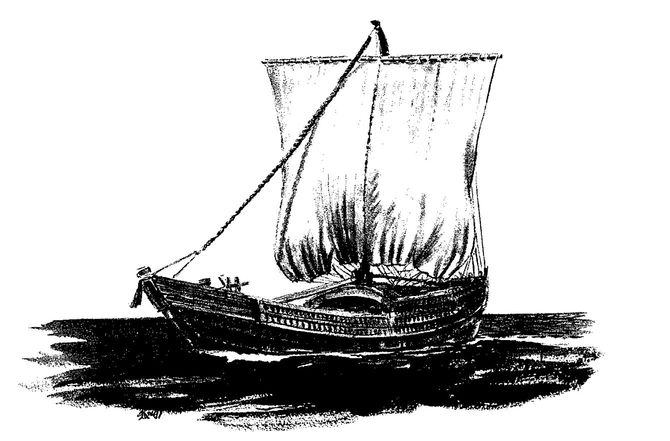※本稿は、椎名誠『漂流者は何を食べていたか』(新潮選書)の一部を再編集したものです。
200年前に漂着した島へ向かうのは現代でも大変
光太夫らの足跡をできるかぎり追っていこう、という計画をたてていた我々は光太夫らのように千石船に乗ってアリューシャン列島にむかうわけにはいかなかったからアラスカからアプローチした(TBS「シベリア大紀行」1985年)。
光太夫らが漂着した頃はアリューシャン列島とはよばずアレウト列島とよばれ、ここからアラスカまですっかりロシア領だった。
1867年にロシアはアラスカを720万ドルでアメリカに売った。あまりにもでかい買い物なのでどっちが得をしたのかいまだにわからないような気がするが、当時はこの不毛の北の大地をロシアもアメリカも持て余していた気配がある。
しかしその後1902年頃アラスカから大金鉱が発見されてアメリカの大儲けと言われていたものだ。1942年頃のアリューシャン列島は太平洋戦争のただなか。日本の海軍が狙っておりこの列島の西部にあるアッツ島とキスカ島を占領している。
我々は7人チームでアラスカから小型機をチャーターしてアムチトカを目指していた。
1970年代はアメリカがアムチトカで5メガトン(広島型原爆の330倍)というすさまじい規模の地下核実験をおこない、もう島としての存在感など何も持っていなかった気配がある。
我々アムチトカ探検隊の7名はコールドベイという、もう地名からしてやる気のない最果ての氷空港と一年中ブリザードという冗談のようにどうでもいい感じの飛行場の要塞兵舎のようなところから出る飛行機を確保した。10日分の食料とその倍のウイスキーを買い、あとはスパゲティと缶詰がほとんどだった。その頃ぼくはスパゲティとマヨネーズと醤油があればあとはなんにもいらない、というタイドを貫いていたので買い物も簡単だった。いざとなればアザラシを捕まえて食う、という道がある。北極圏のイヌイットの生活を見ていてアザラシのステーキに強い関心があり、できれば自分でさばいてみたかった。
「快晴のち霰5万個」の過酷な島
アムチトカには旧日本軍が作った滑走路があるという。それだけの情報で飛行機はとびあがった。
「コールドベイをでたら3層になっているブリザードで何もみえないからその先のエーダックという島に降りることに変更する」と機長は空中にあがって15分後ぐらいに言った。
「あの機長はさっきおれらのプレハブホテルのバーで見たけどあきらかにバーボン満杯、という顔をしてたぜ」
仲間が言う。「でも機長にはなにもさからえないからなあ」
我々の不安はあたってくる。着陸したのはセイミヤというところだった。目的地に接近しているのか遠ざかってしまったのかおれたちにはまったくわからない。
漂流者のたどりついた島に行くのは現代でも大変なのだ。
結局1時間ぐらいかかって雪と氷が待っている荒涼とした島があらわれた。日本軍が40年ぐらい前に作った滑走路は上空からみてもかなりアスファルトが上下に波うっているように見える。春のさざ波の海と間違えて降りていくんじゃないよ。
エイヤッと着陸してから滑走路のどこかが陥没したとしてもおれたちはそれでおしまいだ。
機長はかなりの低空飛行をして40年前に作った滑走路を検分しているようだ。地上係員というのがまったくいないのだからすべて降りていくほうの自己責任だ。
ぼくは機長の斜め後ろにいたのだが機長の横顔が汗で光っていた。何回かタッチアンドゴーをやって「もういいや、勝負!」という感じで飛行機は運命をきめて降りていった。いそいで我々のテント、寝袋、食料をおろし、チャーター機はまるでそこでモタモタしていると滑走路全部が陥没してしまう、というような慌ただしさで帰っていった。約束の日にちゃんと来てくれるだろうか。もちろんどちらにも無線機はない。
すぐにテント(冬山用)を張ろうとしたがこの島の風は一定方向から吹いてくることがなく3、4人用のテントを張るのに1時間もかかってしまった。ちょっとしたものを落とすとすぐ突風でどこかにもっていかれてしまう。そのうちテニスボールぐらいはありそうな雹が降ってきた、というより落ちてきた。あたるとあぶない。
3日もするとわかってきたが、この島に天気予報というものがあったらこうなる。
「今日は曇りときどき晴れかと思うとすぐに雨。しかしたちまち回復するがあっという間に雹もしくはデタラメ方向から霰5万個。そのうちいきなり快晴だが間もなく豪雨になるでしょう。東西南北の風、風力さまざま」