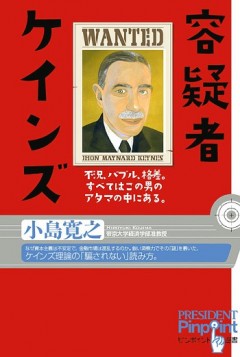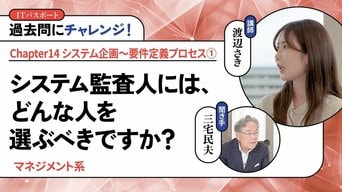ぼくは、昨年(2008年)8月、『容疑者ケインズ』という本をプレジデント社から刊行した。まさにその直後、「リーマンショック」が起きた。リーマンブラザーズというアメリカ屈指の証券会社が破綻したのである。それを契機に、あまりの急ピッチで世界経済の急冷化が進んだ。株価は暴落し、世界中の金融機関が危機に瀕し、自動車の販売が数10パーセントのオーダーで落ち込み、製造業を中心とした大幅な労働者削減が猛スピードで進行中である。
ぼく自身は、自分の本の刊行直後にまさかこれほどまでひどいありさまが発現するとは想像だにしていなかったが、かといって、この本の執筆したことと今度の経済危機が全く無関係なわけでもない。というのも、数年前から、経済学者の間では、アメリカの住宅ブームがバブルであり、ブームを牽引したサブプライム関連金融商品の価格調整が早晩起きることはコンセンサスとなっていた。リーマンショックの起きる1年前(2007年)には、すでに金融業界の変調ははっきりしてきており、「きっとナニカ起きるだろう」ことは多くの経済学者の目には明らかだったのだ。
実際、ぼくは当時連載を持っていたウエブマガジンWired Visionの小島寛之の「環境と経済と幸福の関係」で、「不況の経済学」のこと、とりわけ「ケインズ的なものの見方」について繰り返し解説をした。経済学者として、不況の迫る足音を無意識に聞いていたからなのだと思う。その断片的な解説を大きく膨らませ完全化した本書『容疑者ケインズ』を、リーマンショック直前というみごとなタイミングで刊行できたのは、単なる偶然ではなく、そこそこ必然性のあることだったのだ。
さて、リーマンショック後、世界経済の激変とともに注目すべきことは、経済学者たちの態度の激変であろう。少なからぬ経済学者が、今回のできごとにショックを受けている。自分たちの想像力を越えた事態が目の前で現実となったからである。もちろん、ぼく自身もその1人だ。世界大恐慌という大事件が、1930年代に起きたことは、経済学者なら誰でも史実として知っているし、この事件がその後の経済学の方向性に大きな影響力を持ったことも共有されている。だから、こういう経済危機が可能性としてはありうることは認識している。しかし、「可能である」ということと、「眼前でリアルに起きる」こととはまるで違うのだ。
例えば、著名な経済学者・野口悠紀雄氏は、100年に一度の危機に、ケインズはよみがえるのか?(ダイヤモンド・オンライン)と題して、ケインズ理論を見直したことを告白している。氏は「これまでマクロ経済学などくだらないと考えていた」そうだが、「しかし、いまわかったことは、有効需要の落ち込みというメカニカルなメカニズムも、規模が大きければ、現実世界に重大な影響を与えるということだ。われわれがいま直面しているのは、マクロ経済モデルで分析できる事態である」と述べている。経済学者としての経歴の中で初めて、ケインズ経済学の意義を、(多少は)認めた、という意味だろう。
また、小泉構造改革の急先鋒であった経済学者・中谷巌氏も、近著『資本主義はなぜ自壊したのか』の中で、自分の誤りを認め、「転向」を宣言している。(なぜ私は変節したか?:日経ビジネスオンライン)。
これは、自分の信奉した「アメリカ的新自由主義」が、決して世界に豊かさをもたらすものではなく、むしろ不安定性と危機をもたらすものだと気づき反省した、という趣旨であるが、この「転向」の背後に、今回の金融危機へのショックがあることは疑いないだろう。
目を見張るのは、昨年の終わりから今年にかけて、論壇する経済学者がみなケインジアンになってしまったことである。公共事業などの財政出動やかなり踏み込んだ金融政策の必要性が、あたかもアタリマエのことのように語られている。少し前までは、完全に効果が疑問視されていたはずの財政政策が議論の俎上に載っているのは驚くべきことである。まるで、ケインズが降臨して、たくさんの経済学者やエコノミストや政治家に憑依したかのごときである。一度は葬りさられたはずのケインズ理論がこんな風に蘇ったのは、もちろん、今回の経済危機が、経済学者を含む多くの人の想像を絶したものだったからに他ならない。