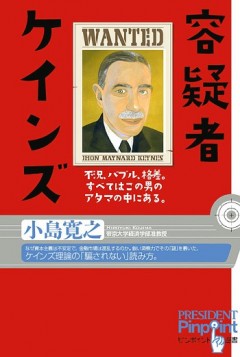ケインズは、この本の中で、「需要の縮小」というメカニズムを論理的に説明してみせた。それは、新古典派の枠組みとは全く異なる視座を持った理論であった。当然である。さきほど述べた通り、新古典派経済学の枠組みでは、無人島の思考実験のように、どうしても「作ることのできるモノは余さず利用される」ことになってしまうからだ。これは「供給は需要を生む」という風に表現され、「セイの法則」と呼ばれる。したがって、不況とか恐慌のメカニズムを描き出すには、伝統的な議論の方法を捨てなければならない。
ケインズが、どうやって伝統的な議論を避けて、「モノが余る」世界を論証したのか、それは次回以降で明らかになる。この連載は、拙著『容疑者ケインズ』の一部をウェブ上で公開するものだ(興味を持ったら他の部分もぜひ読んでいただきたい)。ただし、第1回と第2回、そして最終回は、本に書ききれなかったことをいくつか補足する。今回は、「ケインズの理論がなぜわかりにくく、そして、多くの経済学者から批判されていくはめになったのか」、そのことをしたためる。
ケインズの『一般理論』は、しばらくの間は賞賛を浴びていたが、次第に批判の嵐にさらされていくことになった。それは、この本に、ロジックが錯綜している部分や、根拠なく決めつけている部分や、前後とかみあわない論理展開などが散見されたからだ。簡単にいえば、「ロジックのごった煮状態」になっていた、ということである。
それもそのはずで、ケインズは学者でもあったが、それよりも大蔵官僚という政治家的立場のほうにより親和性があった。だから、首尾一貫したロジックよりも「臨機応変」な考え方をする傾向が強かったのではないかと思う。それが、『一般理論』を「ロジックのごった煮状態」で書いた理由なのだろう。
実際、『一般理論』は、ケインズ1人のものではない。当時のケンブリッジ大学の優秀な経済学者を「ケインズサーカス」として組織した研究会の成果であった。この研究会の重要メンバーは、ジョーン・ロビンソンとリチャード・カーンという2人の学者だった。『世界』(2009年1月号)における、ロビンソンやカーンと交友のあった経済学者・宇沢弘文氏と『一般理論』の文庫版の翻訳者である間宮陽介氏の対談によれば、この本は、当時大蔵省の顧問をしていたケインズが週末にキングスカレッジに帰ってきたとき、カーンが1週間の研究作業を報告して、ケインズがそれにサゼスチョンをする、ということが4年ぐらい続けられ、それをケインズがまとめて刊行したもの、とのことである。しかも原稿は、わら半紙の小さなメモ用紙に殴り書きで、アッという間に書き上げられたのだそうだ。つまり、『一般理論』という書物は、いろいろな学者の考えを、ケインズがあまり熟考もせずに組み合わせて構築した「パッチワーク」のようなもので、それゆえ、「理論書」というよりはジャーナリスティックな色彩が強い本になったのである。
宇沢氏はこんな驚くべきエピソードを紹介している。宇沢氏が1979年にケンブリッジを訪問し、ロビンソンとカーンに毎日会って議論していたある日、カーンがこんなことをいった。自分は去年初めて『一般理論』を読んだ、と。そのあと「書き方がひどい。全く意味が通じない」、と。その時はロビンソンも、あまりのショックで黙っていた、とのことだ。このエピソードでわかるように、ケインズ理論は、その立役者にさえ意味の通じないところがある、ということなのだ。多くの経済学者に混乱をもたらし、批判にさらされて行くのは当然といえば当然に帰結だった。