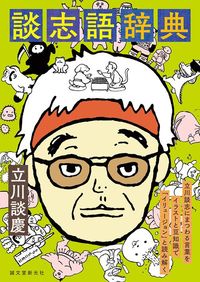流行語を通して「日本人の感受性」を再認識
「ワンチーム」は、まず「他者への気遣い」を前提として組織を一体化させるために機能する言葉です。「そだねー」は、そもそも相手への同意、つまり「他者への気遣い」そのもの。「インスタ映え」は「他者への気遣い」の可視化ですし、そこでの「いいね!」の数が「他者への気遣い」の数値化になります。「忖度」に至っては「他者への気遣い」とほぼ同義語だと辞典にも書かれていそうなことであります。
もしかしたら日本人は、流行語を通して「他者への気遣い」という先祖代々受け継いできた大切な感受性を、再認識したいと願っている国民なのかもしれません。他者のことを「他人様」とか「世間様」とか「様」という敬称まで施してリスペクトしている国は他に果たしてあるのでしょうか。
理想は、いままでのような経済成長などを前提とした「量的なワンチーム」ではなく、LGBTをはじめとした多様な価値観の存在を認める「質的なワンチーム」ではないでしょうか。
無論メダルの数が多いほうに越したことはありませんが、数値目標ではなく、より感動を目指す——日本に期待されるポジションはそんなところだと確信します。
そして、そんな「他者への気遣い」が応酬される空間こそが落語会の会場ではないかと確信しています。
落語は登場人物の会話とその表情だけで成り立つ芸能です。正直余白だらけ。そこの余白部分に観客各位が「想像力」をフルに働かせてはじめて完成する世界です。つまり、演者も観客も同じ場に立つ共感力こそが肝となります。落語会の会場全体がいわば「ワンチーム」なのです。
自分を知らない人は、他者への気遣いもできない
このワンチームはある意味集団催眠の場でもあります。だからこそ落語の最中に鳴る携帯電話はそんな儚い夢のひとときから目を覚ましてしまう凶器にすらなってしまうのです。
今よりもずっと人間同士の密度の濃かったはずの江戸時代に花が咲いたのが落語です。そんな落語家と観客との「ワンチーム」を会場を愛でつつ、観客は落語家に同意の意志表示で「そだねー」と笑いで反応し、「瓦版」という「江戸版インスタ映え」で情報を共有化しながら、みんなで上手に「忖度」し合ってきたからこそ、300年近くにもわたるあの長年の平和が保たれてきたのでしょう。
こうしてみると流行語大賞とは「長年日本人は変わってきていないこと」を証明する儀式にすら思えてさえきますなあ。
そして、「他者への気遣い」とはまず「自分の客観化」からはじまるのではないかと私は考えます。「自分というもの」がどういう存在なのかが客観的に見える人こそ「他者への気遣い」ができるものです。「自分というものは、こういう時に怒るのだ」ということがわかる人は、少なくとも他人を怒らせるような振る舞いはしなくなるはずです。「自分はこういうことをされたら嬉しい」とわかる人は、それを率先してやれば人は喜ぶということを知っているはずです。