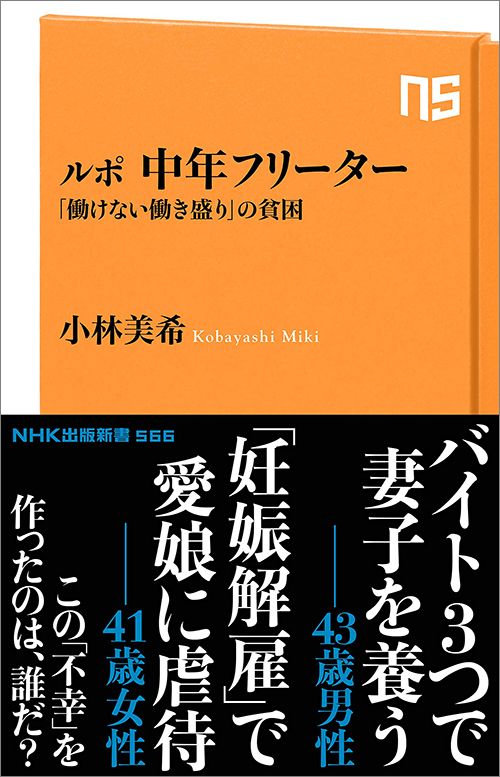はじめて「死」を選ぼうとした瞬間
「自分にはもう、何も残っていない」
元妻と一緒に住んでいたマンションは引き払い、日雇い派遣をしながらシェアハウスで暮らすようになった。
シェアハウスは、使わなくなった町工場を再利用したもので、そこに三〇~四〇人が住んでいる。中はパーテーションで仕切られ、二畳ほどのスペースに二段ベッドが無造作に置かれただけの部屋がある。しみついた油の臭いがきつい。ほこりっぽく、すぐに喉を痛めた。お金がなく、病気になっても病院には行けなかった。いつも前向きな健司さんも、この時ばかりは死を考えた。
それでも、望みは捨てなかった。派遣会社は仕事の紹介をしてくれる。それが地獄のような生活のなかに降りてきた、自分を救ってくれる蜘蛛の糸のように見えた。
「日雇い派遣でも、毎日仕事があるだけ良いのかもしれない。正社員になれたとしても、好業績が続かなければリストラされる。倒産すればもともこもない。だったら、誰も頼らず、独立を考えたほうがいいのだろうか」
二年ほど日雇い派遣で生活しながら求職活動もし、独立の可能性も探っているうち、正社員になるチャンスが到来した。
最初は契約社員での入社だった。ベンチャーのIT企業で、社長と上司と健司さんの三人で事業をスタートさせ、三年半の間に従業員は一〇人ほどに増えた。初めての「月給」をもらうと、やがて明確な契約がないまま正社員登用された。月給は手取りで一七万~一八万円だ。大手アパレル会社の本社に、「ヘルプデスク」というITサポート事務員として常駐する。取引先で起こる、レジなどのシステムトラブルへの対処が仕事だ。
たった一度きり経験した「正社員」
だが、日中は店舗ごとにパソコンの導入や試行があり、その間にも故障などトラブルで問い合わせの電話が鳴りっぱなしだった。夜にならないと、集中して現場にかかりきりになれない。業務時間内ではとうてい仕事は終わらなかった。週末には、全国に二〇〇ある店舗のあちこちから、一〇〇件を超えるヘルプが来る。
あまりの激務に逃げるようにして職場を去った。健司さんが「正社員」を経験したのは、この一度だけで、結局は今も日雇い派遣などで職を得ている。
健司さんのような働き方は、社会保障制度からこぼれ落ちてしまい、病院にもかかれない事態に陥る。非正規雇用では民間の保険に入る余裕もない。
しかし、こうした非正規でも安心して働くことを支える仕組みがある。労働組合が運用している共済だ。たとえば日本医療労働組合連合会では、医療や介護職場などの労働者に向けた「医労連共済」を運用している。労働組合に入ることが共済の加入条件となっており、非正規雇用労働者でも組合員の家族でも加入できる。「生命共済」「医療共済」「交通災害共済」をあわせた「セット共済」の掛け金は、最小で月額八〇〇円と加入しやすい。インフルエンザなど病気で五日以上休んだ場合でも、休業給付が受けられるのが特徴だ。時給制や日給制で働く非正規雇用労働者にとって、ありがたい制度だろう。日本医労連の共済担当者は「共済と労働組合に同時に入ることで仲間もでき、職場で孤立しなくなる。労働条件の改善についても交渉しやすくなる」と話す。
こうしたセーフティネットこそ、国が構築すべきではないだろうか。
労働経済ジャーナリスト
1975年茨城県生まれ。神戸大法学部卒業。株式新聞社、毎日新聞社『エコノミスト』編集部記者を経て、2007年より現職。13年「『子供を産ませない社会』の構造とマタニティハラスメントに関する一連の報道」で貧困ジャーナリズム賞受賞。著書に『ルポ 保育格差』など。