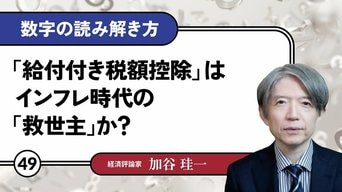試合後にも分かれた評価
女子テニスの大坂なおみ選手が、全米オープンで優勝した。20歳の大坂選手にとって初めてのグランドスラム(四大大会)のタイトルである。相手は、23回のグランドスラム優勝歴を持つ、元世界1位、セリーナ・ウィリアムズ。出産を経て復帰、第50回の全米オープンで、24回目のグランドスラム優勝を目指していた。
大坂選手のプレイはすばらしかった。一方、試合は、主審からウィリアムズ選手が「試合中にコーチの指示があった」として警告を受け、「ラケットを破壊した」として1ポイントのペナルティ、「審判に暴言を吐いた」として1ゲームを失う、という異例の展開になった。ウィリアムズ選手がこの間、主審や大会審判部に激しく詰め寄るシーンが再三あったこともあり、なんとも後味の悪い試合になった。
各国のメディアやSNSを見る限り、荒れた試合の中で、最後まで集中力を切らさず戦った大坂なおみ選手に対する称賛と敬意が寄せられる一方、ウィリアムズ選手の言動に対しては、極めて否定的・批判的なものも含めて、さまざまな見方がされているようだ。
改めて問い直してみたい。
2人は、何と戦い、何に勝ったのか。あるいは負けたのか。
「勝つ」ことに集中するために「見ない」
類いまれなる才能を評価されながら、生かし切れていなかった大坂選手の最大の敵は、「自分の精神面の脆さ」だったに違いない。試合中にうまくいかなくなると、ラケットを放り投げたり、涙を流したり、またセット間にベンチでタオルを被って「もういやだ、やりたくない」と泣き言を言ったりしていたのも、つい最近までのことである。
ところが、今回の全米オープンでは、明確に「勝利を目指す(Play to win)」を貫いていた。決勝を前にしたインタビューでも、ウィリアムズ選手が子供のころからの憧れの選手であり、彼女と全米オープンの決勝で対戦することが夢であったことを語っている。一方で、「ウォームアップまでは、憧れの選手、として見ていたが、試合が始まったら、単なる1人の対戦相手、と見た」と言っている。
荒れた試合の中でも、集中力を切らさなかった。試合後の会見では、ウィリアムズ選手の試合中の審判に対する猛抗議に関して、「背中を向けていたのでわからなかった」、「観衆の声が大きくて聞こえなかった」と述べている。
私はこれをウィリアムズ選手に対する配慮を含むコメントだと捉えていたが、その後の米国の人気トークショーででは、「何が起こっているのか、本当にわからなかった」とし、「小さいころから、(試合中に)相手が怒ったりしているようなときも、それを見ないようにすることを教えられてきた。別の方向を見て、集中できるようにトライするよう教えられてきたから、そうしようとしていた。心の中では、何が起こっているのか知りたいと思っていたけれど」と語っている。意識的に目をそらすことで、「試合に勝つ」という目標に対する集中力を切らさなかったのだ。