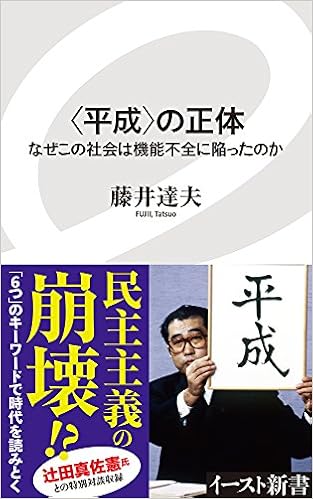「愛国ソング」炎上はなぜ起きたか
【藤井】最近音楽の分野では、バンドRADWIMPS『HINOMARU』や、ゆずの『ガイコクジンノトモダチ』の歌詞は愛国ソングであると一部の人々が問題視しました。辻田さんは軍歌についても研究されていますが、現在のこのような潮流についてどう捉えていますか。
【辻田】昭和初期はコロムビアやビクターなど、現在もある有名なレーベルが確立し、音楽産業の原型ができた時代です。音楽産業は、エロ・グロ・ナンセンスの時代は流行歌でしのぎを削っていましたが、満洲事変や日中戦争が勃発すると仕事のために軍歌をつくるようになります。思想信条があったわけでもなく、全部が全部押し付けだったわけでもない。むしろ軍歌にはビジネス的な観点が強くありました。
戦前の反省を踏まえ、戦後は国威発揚的な音楽には抑制的な傾向がありました。ところが平成になり、昭和の歴史が遠くなっていく中で、そういった歯止めがきかなくなっていると感じます。歌詞をよく見ると、そこまで問題にすることか……とは思いますけども。ただRADWIMPSやゆずといった、特殊な思想を前面に押し出していない人たちが歌詞を書いたことには注目しています。
ちなみに北朝鮮にはモランボン楽団というグループがあって、K‐POPのような音楽を取り入れて愛国歌や軍歌を発信しています。軍歌は古臭いものの復活や勇ましいものではなく、最近の音楽と結びつくことがよくわかります。
【藤井】2020年の東京オリンピックを、ナショナルな運動として、安倍政権をバックに、盛り上げたいと思っている人たちもいるのでしょう。今の忖度の政治を見ていると、音楽業界も忖度したのだろうと思います。RADWIMPSやゆずが自らああいう曲をつくったというよりは、そうした愛国的な空気を敏感に感じたのではないか。その意味で戦前の軍歌と似た部分を感じました。
【辻田】昭和初期と違う点は、グローバル市場で勝負していることです。国内のみならず、海外の目を気にしなければいけません。行き過ぎたナショナリズムは批判されます。もうかるからナショナリズムをあおるのではなく、お金のためにナショナリズムに歯止めをかける動きは出てくるでしょうね。国威発揚イベントの際には、どうしても国威発揚的な音楽が生まれます。そのときにナショナリズムとグローバリズムのどちらを取るのか。エンタメ業界では選択を迫られる機会が増えるでしょう。