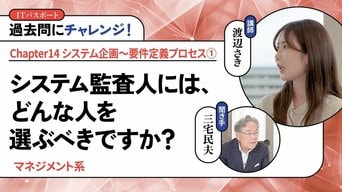危機の本質は、その予想不可能性にある。経験が役に立たない世界だ。それだけに、情報不足になりがちで、それが被害を拡大させる。この負のスパイラルに陥らないためには、いかなる情報対策を講じればよいのか。
航空業界の雄、ボーイング社は、過去15カ月間にわたって予想もしない事態の連続に遭遇し、同社の危機における情報戦略が試された。2001年2月に本社のあるシアトルで地震があり、5万人の従業員を何棟ものビルから緊急に退避させねばならなかった。翌月、同社がシアトルからの本社移転計画を発表すると、地域の反応は予想以上に否定的だった。さらに9月11日の事件によって同社の財務見通しは劇的に悪化、最大3万人の社員のレイオフを考えざるをえなくなった。だが、ボーイング社は一連の経験を通して、危機における同社の情報伝達体制が万全であることを確認できたのである。
たとえば地震発生後わずか数時間でウェブサイトを立ち上げ、社員に翌日も業務が可能である社屋がどこかを伝えた。情報担当責任者はオフィスおよびコンピュータへのアクセスがないにもかかわらず、午後にはプレス・リリースを出した。「危機においては、経験が習熟をもたらすという学習曲線は存在しない」とボーイング社で危機対策と情報計画担当マネジャーを務めるディーン・トーガスは力説する。「危機対策担当者は、危機が発生したら即座に対応できなければならない。日頃から訓練を積み、インフラを整備することが不可欠なのだ」。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント