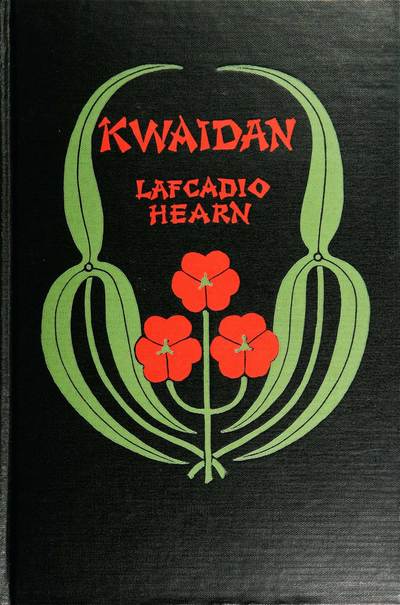※本稿は、池田雅之『小泉八雲 今、日本人に伝えたいこと』(平凡社新書)の一部を再編集したものです。
日本が西洋化した時代に西洋からやってきた
日本がまさに西洋化の波に吞み込まれつつあった明治時代――。失われゆく古きよき日本の心を、独特な感性と偏見のない公平な視座をもって、克明に書き記し続けたアイルランドとギリシャの血を引く小泉八雲(1850〜1904)。その波瀾に満ちた生涯と今を生きる私たちに遺したメッセージとはどのようなものだったのでしょうか。
小泉八雲は、イギリス人ラフカディオ・ハーンとして1890年4月4日、39歳の時に来日し、その6年後に日本に帰化、54年の生涯を日本人として終えた文学者・教育者です。
「耳なし芳一」や「雪女」などを収めた『怪談』の作者として、ご存じの方も多いことでしょう。しかし、八雲はそれだけでなく、紀行文やエッセイ、評論などを通じて、西洋化の波に吞み込まれる直前の、慎ましく誠実な日本人の暮らしぶり、暮らしに息づく信仰心、美しい自然などを克明に私たちに書き残してくれた作家です。
外国人だった八雲の目をとおして描かれる日本を知ることで、今一度、日本文化とは何か、また日本人とは何かを見つめ直すことができるように思います。
そして、さまざまな文化的背景をもっていた八雲は、異文化に対して柔らかく公平な、独特な視点をもっていました。そのような視点は、世界各地でさまざまな文化・文明間の対立が起きている現代社会において、極めて示唆に富むものといえるでしょう。
独自の異文化理解を培った出自と生い立ち
八雲は1850年、アイルランド人の父チャールズ・ブッシュ・ハーンとギリシャ人の母ローザ・アントニア・カシマチの間に、ギリシャのレフカダ島で生まれました。
その後まもなく、軍医であった父チャールズは西インド諸島に赴任し、八雲は母ローザとともにアイルランドのダブリンに移住します。
八雲が3歳の時に父は戻ってきますが、母ローザへの愛はすでに冷めていました。母も異国の生活に馴染めなかったのか、神経の病を発症して、故郷のギリシャに帰ってしまいます。以後、4歳の八雲は二度と母ローザに会うことはありませんでした。
そして、昔の恋人と再婚した父も、八雲をダブリンに残したままインドに赴任し、病死してしまいます。
こうして八雲は幼くして、天涯孤独の人生を歩み始めます。