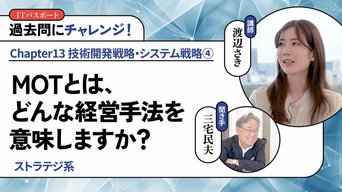幼児期の発達の兆候が、将来的にADHD(注意欠如・多動症)を発症する可能性を示す手がかりになるかもしれない。この段階で適切なサポートができれば、子どもたちの将来に大きな違いをもたらす。
脳の配線(神経回路)はこの時期に形成され、注意力に関わるスキルの土台となる。この発達の過程を把握することで、将来ADHDを発症する可能性のある幼い子どもを早期に見つける手がかりになる可能性があると、カナダ・サイモンフレーザー大学(SFU)の研究者らは結論づけた。
彼らは、脳の構造と機能が「重要な」初期の数年間にどのように発達し、相互に作用するかを調査した。「都市にたとえるといい」と話すのは、論文の著者で、SFU神経科学・神経技術研究所(INN)創設者のランディ・マッキントッシュ氏だ。
「道路が脳の構造で、交通が脳の活動だ。この年齢の子どもにとっては、道路の整備具合、つまり脳の構造が特に重要になる。道路がうまく造られていなければ、交通はスムーズにいかない。それが、子どもが集中したり、課題を切り替えたり、注意をそらすものを無視したりする力に影響を及ぼす」
「遺伝、胎児期の影響、そして幼少期の経験が、脳の配線に影響を与える可能性がある」
「こうした要因の違いによって、注意力を支える脳内ネットワークの発達に差が生じる可能性も。今回の研究では、一般的な発達の中で注意力に関係するパターンを特定した。これは、今後ADHDに見られる逸脱や、それに影響する要因を研究する際の基準となる」とマッキントッシュ氏は語る。
これまでの研究を踏まえ、構造的および機能的な脳のつながりの変化を同時に調べることで、健全な神経発達のパターンや、将来の行動傾向を予測する要因の理解が進むと、研究チームは指摘する。
今回の研究では、4歳から7歳までの子ども39人を対象に1年間追跡。MRIスキャンを用いて、脳内の構造的・機能的な接続性を測定した。参加した子どもたちは、持続的注意(集中力の維持)、選択的注意(気を散らす刺激を無視する力)、実行機能的注意(タスクの切り替え)の能力を評価する課題に取り組んだ。
研究チームは、グラフ理論を応用して分析を行った。これは、数学的な構造を用いて社会ネットワークなどを調べる手法で、今回は脳内の各領域がどのようにつながっているか、そしてその結びつきが時間とともにどう変化するかを解析するために用いられた。
その結果、脳内ネットワークが「仲の良い友達グループ」のように、特定の領域同士で強く結びつき、他のグループとの接続が少ない構造になっている場合、注意力に関する課題の成績が低くなる傾向が見られた。