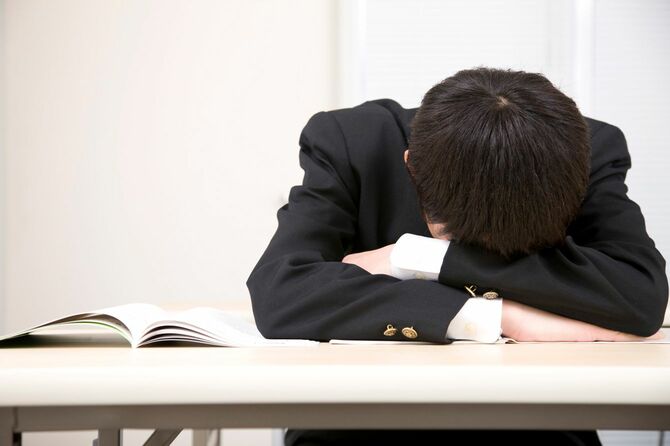不登校から半年後、子の多くが考えること
様々なケースがあり一様ではないが、植木さんによると、子どもが学校に行けなくなって最初の3カ月ぐらいは「急性期」といって、子どもは心身ともに不安定な状態であることが多いという。
その間に親子間のバトルが起きることもあるが、半年ぐらい経つとその生活に慣れていく。そして子どもは、安心できる家の中で落ち着いてくる「充電期」に入るという。
この「充電期」にエネルギーが溜まってくると、「そろそろ何か動こうかな」と考える子が多くなり、次の居場所を具体的に検討する家庭が増えるという。

ここから先は無料会員限定です。
無料会員登録で今すぐ全文が読めます。
プレジデントオンライン無料会員の4つの特典
- 30秒で世の中の話題と動きがチェックできる限定メルマガ配信
- 約5万本の無料会員記事が閲覧可能
- 記事を印刷して資料やアーカイブとして利用可能
- 記事をブックマーク可能