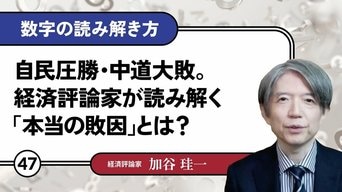笑いには組織における「潤滑油」の機能がある。周囲をリラックスさせ、職場の雰囲気を和ませることは、仕事を進めるうえで有用だとされている。そのため、現代の会社組織では、「人を笑わせること」が、一種の能力として評価されるようになっているかもしれない。
私の専門分野の感情社会学の用語でいえば、人を笑わせる能力は「感情資本」のひとつだといえる。職場に引きつければ、円滑な人間関係を形成するためのコミュニケーション能力のことだ。「資本」と呼ぶのは、こうした能力は、親や家族環境から受け継ぐ要素が大きいと考えられるからだ。独学やセミナーなどでこの能力を学習することは難しい。だからこそ、人それぞれの感情のスタイルを「個性」と呼んでいたわけだろう。
だが現代社会では、この感情資本の「多寡」が問題とされる。たとえば就職活動において、かつて重要だった在学中の成績はいまや学生の関心外である。学生たちが気にするのは「面接官にどう思われるか」という点だ。実際に企業側も、面接などで学生の感情資本の多寡をチェックしている。最近では、SNSを通じて、学生の交友関係を調べる企業もあると聞く。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント