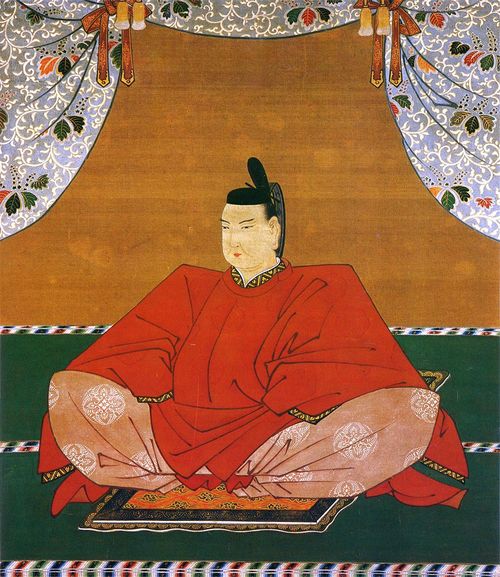外戚が道長の権勢に対抗できなかった
三条天皇は東宮時代が長く、天皇即位後に迎えた道長の娘妍子以前に、娍子との間に敦明親王が誕生していた。娍子の父済時は師尹の二男で「小一条大将」と呼ばれた。済時は敦明親王誕生の翌年に死去しており、その点でも後見亡き母子の立場は厳しいものだった。
眼病を患った父三条天皇は、この敦明親王への皇位継承を前提に譲位することになったが、結果的には空振りとなった。
以上、2人の親王について共通したのは後見なき弱さだった。一条天皇そして三条天皇と、それぞれに分別ある天皇を父に持ちながら、かつ父の天皇たちの期待を背負いながらも外戚の力量に限界があったが故に、道長の権勢には抗し切れなかったことになる。
道長と一条天皇の論理の決定的違い
残念さを残した2人の親王たちだったが、彼らの父、すなわち一条・三条両天皇も無念が残った。道長は特段の陰謀をなしたわけではない。けれども、存在としての重さが、天皇たちの力をも無化する方向に働いた。このあたりが、道長が「専横」の権化とされる所以でもあったろう。「藤原氏擅権」(『国史眼』)などの呼称で、近代以降の史書でも紹介されてきた。
考えてみれば一条と三条の両天皇との関係如何が、その後の政治の安定度に繫がったともいえる。道長の皇太子選定の論理は、外戚確保に向けての恣意性として、しばしば解釈される。が、見方を変えるならば“王権”(天皇を中心として太上天皇や皇后及びその実家などにより体現される権力)内部での安定性への方策でもあった。
一条天皇の皇位継承者への選択眼には厳しい現実への考慮がはたらいていた。不安定な王権の現出による混乱の阻止であった。
敦康親王についての道長の存念と、一条の無念さは、立脚する論理を異にした。道長の存念とは、後見なき親王の孤立に由来する政治基盤の弱さが動揺を招きかねないとの思惑だった。
一条の無念とは、自己の信念を貫くことができなかったことへの後悔だ。自身の弱さへの悔悟に他ならない。道長の立場としては、一見すれば私的な権力欲の推進のための“私の論理”のようだが、公権の体現者たるべき天皇への途は、“外戚力”が前提との考え方だった。その点では、一条天皇の敦康親王への想いは、亡き定子への情愛に支えられていたとしても、“公の論理”ではなかった。