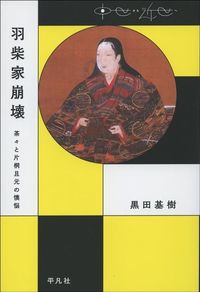石田三成の旧領は徳川四天王の井伊直政に与えた
しかし、それだけではなかった。家康は、自身の一門や宿老にも、敵方からの没収地や味方大名の転封後の地の宛行を行った。福島正則が安芸・備後2カ国に転じたあとの尾張国には、四男松平忠吉を入れ、改易された石田三成領には宿老井伊直政を入れる、といった具合である。そうして尾張国までの東海道・中山道筋は、徳川家の一門・譜代大名で固められることになり、しかも、それら家康取り立ての大名たちは、それまでの羽柴政権下における大名と同列に位置づけられることになった。
それまでの諸大名にとって、合戦後は、家康は主人に相当する立場になり、松平秀康や松平忠吉らその一門衆は、自身より上位者になり、そして宿老で領国大名になった井伊直政や本多忠勝らは、自身とまったく対等の大名として存在するようになったのである。もっともこの時の領知宛行において、家康は宛行状を出していない。このことから、この領知宛行は、家康が完全に「天下人」の地位についたわけでないことを意味するととらえられている。
征夷大将軍になる2年前、家康は大名たちの主君になっていた
いってみれば、この時の家康による領知宛行は正式のものではなく、秀頼の「代行」としてのものであり、そのためこれによって家康と諸大名との間に、ただちに主従関係が成立したわけではない、ということであろう。しかしその一方で、長岡(細川)忠興の場合にみられるように、大名たちにとって、領知を与えてくれたのは家康である、という認識がもたらされていた。決して秀頼からのものとは認識されなかった。
合戦の結果、家康が諸大名に対する領知宛行権を掌握したのは、確かなことと考えられる。そうして慶長7年(1602)からは、家康による領知宛行状もみられるようになっていくことになる。