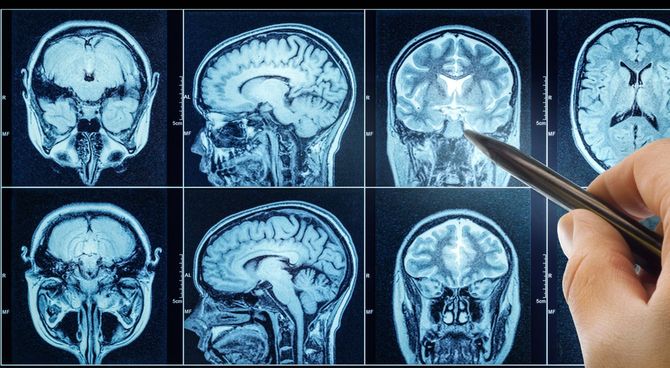いったん認知症になった人に投与しても良くなるはずはない
同じようなAβオリゴマーの抗体ガンテネルマブ(また別の会社が作ったものです)は効かなかったと報告されました。
治験によると、同じオリゴマーの抗体でも、レカネマブとドナネマブは効いて、別企業のガンテネルマブは効かなかった。つまりどちらにしても、ギリギリの線であるというのが現状です。
データを見て気づくことは、根本治療の割には、結果が良いか悪いかのギリギリの数値です。どうしてこういうことが起こったと思いますか? それは、実は、患者さんの問題なのです。つまり、いったん認知症になった人に投与しても、認知症の人は神経がなくなって壊れた人ですから、いくら治療しても良くなるわけがありません。だから、このような治験をするためには、認知症になりそうな人を選んで治療しなければいけないのです。なりやすい人を対象に、何もしない場合(対照実験と言います)と薬を投与した場合を比べないといけないのです。ここがアルツハイマー病治療の難しい点です。
「アルツハイマー病になりやすい人」を見つけて治療する難しさ
もう一つは、最大25年間も治療しなければいけないのです。それも大変です。注射1回か2回で治るようなものではありません。ところが今の臨床試験は、最大2年ほどで結果を出さないといけないのです。そのために、ギリギリの結果でも有意差があればいい、という判断になってしまいます。その2つの問題で、このアルツハイマー病の治験はうまくいっていない場合が多いのです。
そうしますと、私が言ったようにアルツハイマー病になりやすい人を見つけて治療しなければいけません。そうすると対象は脳に老人斑がある人か、アポE4遺伝子(アルツハイマー病を引き起こす原因遺伝子)を持っている人です。ここにも微妙な問題があります。治療しようとすると、その人がアポE4を持っていて、将来ぼける可能性が大きいことが本人にも分かります。本当はそういうことを知らせたくない。なぜかというと、本人が分かってしまうと、下手すると本人がうつ病になる場合もある。だから、このような研究は非常に難しいのです。また二十何年も投与しなければいけないとなると企業にも大きな負担になります。