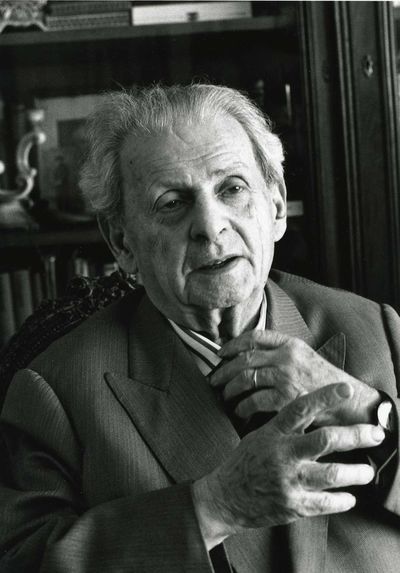来るはずのない仕事が「トリクルダウン」してきた
そういえば、僕がエマニュエル・レヴィナスの翻訳をすることになったのも、そんな流れでした。時代的にはもうちょっと後、’80年代の初めですけれども、ある出版社が「フランスではレヴィナスという哲学者が注目されているようですので翻訳出したいんです」と僕の指導教官だった足立和浩先生のところに電話をかけてきました。
足立先生はフランス現代思想の分野では「知らないことはない」「なんでも来い」という誠にタフな研究者でしたけれど、さすがにレヴィナスには難色を示して、たまたまその時かたわらにいた僕に「おい内田、お前、レヴィナスのこと論文に書いてたよな。ちょっと電話替われ」と受話器を渡したのです。
その電話で僕は出版社の若い編集者相手にレヴィナスがいかに偉大な哲学者であるかを切々と語り、「じゃあ、内田さんがお薦めする『困難な自由』を訳すことにしましょう」という話がその場でまとまったのでした。
そんなことになったのも足立先生のところに仕事がじゃんじゃん来過ぎて、先生の処理能力を超えてしまったからです。だから、たまたま先生の横にいた「猫の手」であるところの駆け出しの研究者に、ふつうなら来るはずのない仕事が「トリクルダウン」してきた。「トリクルダウン」という言葉は、こういう時に使いたいですね。
若者に「恐怖」や「怯え」を強制する空気
勢いがあるというのは、僕の実感としては「そういうこと」です。仕事が増え過ぎたせいで、小うるさい条件とかなしで、若者にさまざまな面白い仕事が回ってきた。そういう時代が1960年代の初めから始まって、’90年代の半ばくらいまで続きました。
この時代の雰囲気を「勇気」に絡めて論じるのはちょっと難しいかも知れませんが、それでも若者たちに「恐怖」や「怯え」を強制するという空気はあまりなかったように思います。
僕がある大手商社に営業に行った時に、話を聴いてくれた人が、「わかった。じゃあ、君の会社ができそうな仕事をしている部署にいま電話かけるから、君、この場で営業してごらん」といきなり電話をかけて「はい」と受話器を渡されたことがありました。