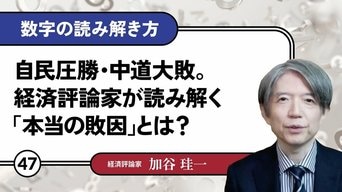※本稿は、内田樹『勇気論』(光文社)の一部を再編集したものです。
日本に「勢い」があった時代
1970~90年代の日本の組織はどこも「勢い」がありました。「勢い」というのはただ金が儲かるということではないんです。とにかく仕事がどんどん増えてくる。それもやったことのない仕事が。
僕は’75年に大学を卒業してから2年近く定職に就かずふらふらしていました。一応「大学院浪人」を自称していたので、フランス語とフランス文学史の勉強だけは一日3、4時間くらいしていたのですが、あとは自由時間です。でも、家賃も払わないといけないし、ご飯も食べないといけないし、お酒を飲んだり、麻雀したり、スキーに行ったりもしなくちゃいけないので(いけないということはないんですけど)、生活費を稼がねばならない。
その頃の生業はほとんど友だちから回ってきたものでした。「内田、暇なんだろ?」という前口上付きで仕事が降ってくる。頼まれた仕事は家庭教師でもなんでもやりました。主な収入源は英語とフランス語の翻訳でした。それだけで暮らせたわけですから、ずいぶん熱心にやっていたんですね。それに翻訳だと「受験勉強も兼ねている」という(自分に対する)言い訳も立ちますから、頼まれたら片っ端から引き受けました。
平川克美氏と翻訳会社を起業した
のちにその頃よく仕事をしていた翻訳会社で内勤のバイトをした時に「外注翻訳者リスト」があって、その中に僕の項目もありました。なんて書いてあるのかなと思ってそっと盗み読みしたら「技術系は弱いが、仕事は速い。料金は最低ランク」という評点がついておりました。「速くて安い」ファストフードのような翻訳者だったのでした。
’77年の暮れに平川克美君から「翻訳会社始めるけれど、内田もやらない?」というお誘いがありました。平川君は僕がバイトをしている翻訳会社に僕が引き込んだのですが、仕事のノウハウをすぐに覚えて正社員になりました。忙しく働いていたのですけれども、会社がかなりブラックな雇用環境で、翻訳者や通訳からの「中抜き」がかなりだったので、もっと労働分配率の高い、働く人にやさしい環境を作ろうとして、独立することになったのでした。その時に平川君から「内田、暇なんだろ?」と誘われて、一も二もなく起業仲間に加わりました。