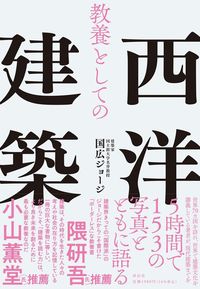実際、サリヴァンはオーディトリアム・ビルとはずいぶん印象の異なるビルも設計しました。「カーソン・ピリー・スコット・ストア」という百貨店がそれです。装飾がほとんどなく、ジャングルジムのような構造がそのまま見えるあたりは、かなり近代的な感覚です。
このビルの特徴のひとつは、道路の交差点に面した角の部分がカーブを描いていること。バーナムのリライアンス・ビルやサリヴァンのオーディトリアム・ビルもそうですが、オフィスビルは玄関のある側が「正面」です。でもカーソン・ピリー・スコット・ストアは商業ビルなので、人通りのある道の両方からお客さんを集めたい。だから角にカーブをつけて、そこを玄関にしているわけです。
サリヴァンの作品には、ほかにも有名なものがいくつかあります。たとえば、1891年に完成した「ウェインライト・ビル」と、1895年に完成した「ギャランティ・トラスト・ビル」。どちらも基壇、ボディ、飛び出した屋根という似たような構造ですが、この2つは、ある意味で対照的な個性を持っていると思います。
ビルに表れる建築家の個性が面白い
ウェインライト・ビルは、4つの角を太い柱が支えていることで、水平性よりも「上」へ向かう垂直性が強調されています。屋根は分厚く、全体的に力強い。僕には、このビルが「男性的」なものに感じられます。
一方のギャランティ・トラスト・ビルに、そのような強さはありません。角の柱が細く、全体に編み物のようなやわらかさがあります。そのため、どちらかというと女性的なイメージ。男女の性質を一面的に決めつけてはいけませんが、古代建築の円柱にも、男性的なドリア式と女性的なイオニア式がありました。
同じ建築家が、このように個性の異なる作品を手がけていることが、僕にはとても面白く感じられます。こうやって、「建築を読む」という鑑賞方法をゲーム感覚でやることで、建築に対する親しみや楽しみが増えるのではないでしょうか。
ところで、サリヴァンのカーソン・ピリー・スコット・ストアは、まったく装飾がないわけではありません。2階から上は、のちのモダニズムにも通じる機能性重視のデザインですが、通りを行き交う人々が目にする1階には花模様などの装飾が施されました。これは、1890年代から20世紀初頭にかけて流行した「アール・ヌーヴォー」という様式を取り入れたものです。