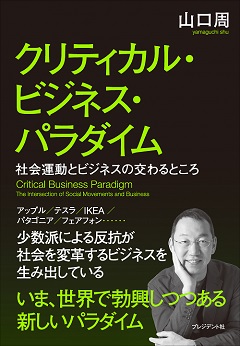品質や機能ではなく、「哲学」を売っている
「モジュラーデザインの採用」も「ライフサイクルの延長」も「リペアラビリティの向上」も、直接的に顧客に何らかの便益を与えるものではありません。言うなれば、フェアフォンは、既存の競合メーカーに対して、後発として差別的優位になるような顧客便益を、何一つとして提供していないまま、参入に成功したのです。これは驚くべきことです。
もちろん、アップルやサムスンといった大手スマートフォン・メーカーもサステナビリティに関する取り組みを進めてはいますが、フェアフォンとは取り組みの位置付けが異なります。アップルやサムスンにおいて、競争優位の形成は主に、デザイン・技術革新・ブランド・マーケティングの強化によって追求されています。
一方で、フェアフォンの場合、これらのサステナビリティに関する取り組みそのものが、顧客を惹きつける要因、競合に対する競争優位を生み出す意味を形成しているのです。
フェアフォンが、新興のスタートアップであったにもかかわらず、非常に競争の激しい市場において一定の存在感を持つまでに成長できた理由は、製品の品質や機能が優れていたからではなく、彼らが、既存のビジネスの慣習に慣れきってしまっている業界や市場に対して、彼ら自身の哲学に基づいて批判的=クリティカルな提言を行ったからです。
「修理代が高いから買い替える」状況はおかしい
彼らの批判的提案に共感した人々が、顧客を中心としたステークホルダーとして集まることで、フェアフォンの提案が一種の運動として社会変革のうねりを生み出しているのです。
実際に、フェアフォンの創業者たちは「私たちがやっているのはビジネスというより『修理する権利を取り戻す』という社会運動なのです」とインタビューにおいて答えています。彼らはまさに「社会運動としてのビジネス=クリティカル・ビジネス」を運営しているのです。
従来、修理を検討しているユーザーが取れる選択肢は「メーカーが認めた公式修理サービス」の一択で、それ以外を利用すると製品に付帯するメーカー保証自体が消えてしまうのが一般的でした。このような状況下では、メーカーが修理費用を高額に設定できたり、またそうすることで、修理ではなく新製品の買い替えにユーザーを誘導できたりします。
結果として、廃棄物は増え、ユーザーは不当な出費を強いられることになります。
多くの人は、このような問題の存在にうすうす気づいてはいたものの、相手が巨大な権力を持つ大企業であることから、「仕方がない」「そういうものだ」と諦め、不本意ながら現状を受け入れていたのですが、そのような状況に対して、フェアフォンは「このような状況はおかしい、修理する権利を取り戻そう」という社会運動をビジネスというフォーマットを用いて始めたわけです。