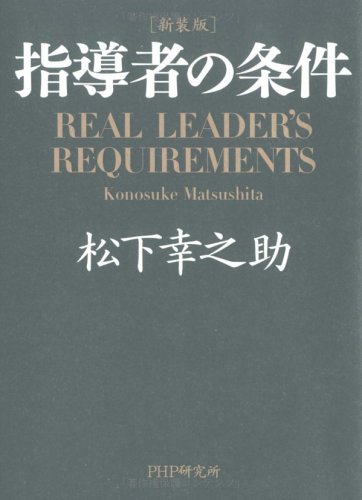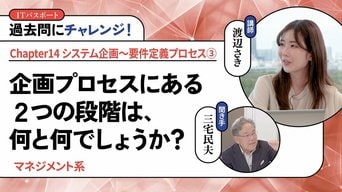日本の経営者やミドルはいつからか叱らなくなった――。経営学の泰斗である加護野忠男氏は言う。かつては叱ることで人を育てる文化が日本企業に根付いていた。今こそ、「叱り上手」の名経営者に教えを請おう。
メールでの叱責はタブーである
今の会社組織は叱り方を忘れているように見える。その一番単純な理由は、みんな叱られ慣れていないことだろう。団塊の世代が入社した頃は、まだ会社では叱るという行為がずいぶん行われていた。しかし、団塊の世代の人たちはそのありさまを見て、こんなことをやってはいけないと考えて、あまり叱らなくなったように思う。

セブン&アイ・ホールディングス
CEO 鈴木敏文
1932年、長野県生まれ。イトーヨーカ堂創業者の伊藤雅俊元社長の懐刀として、セブン-イレブン・ジャパンを創設。日本におけるコンビニエンスストアの礎を築いた。ジャーナリスト勝見明氏の著書『鈴木敏文の「話し下手でも成功できる」』では、部下や顧客を説得するための鈴木氏のテクニックが描かれている。
CEO 鈴木敏文
1932年、長野県生まれ。イトーヨーカ堂創業者の伊藤雅俊元社長の懐刀として、セブン-イレブン・ジャパンを創設。日本におけるコンビニエンスストアの礎を築いた。ジャーナリスト勝見明氏の著書『鈴木敏文の「話し下手でも成功できる」』では、部下や顧客を説得するための鈴木氏のテクニックが描かれている。
叱り慣れていない人々が部下を叱ろうとするとき、どのような点に気をつければよいか。基本は仕事に、会社にコミットすることである。コミットがなければ「叱らないほうが得」という考えに流れてしまう。
そのうえで、何よりも重要なのは自然な感情の表出である。感情の表出の大きさは、志や企業精神を伝える重要な手段だからである。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント