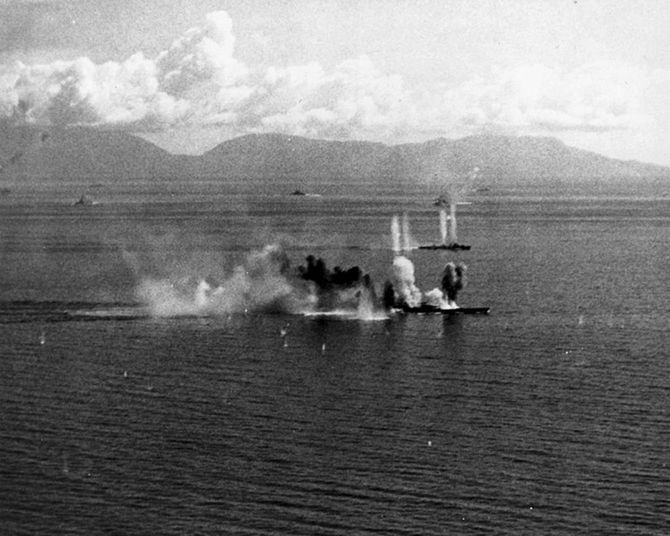新しいデータをもとにすれば、被害は小さかったかもしれない
予想と実際のデータがあまりにも大きくずれたのは、当然予想の詰め方が甘かったからである。
では真面目に科学的に詰めた結果のデータであったのか、となると怪しい。たとえば艦船の消耗量の推計である。作製したのは海軍軍令部第4課であった。同盟国であるドイツの戦果をもとに、連合軍と開戦した場合の日本の被害を推計した。
1941年10月下旬に着手し急いで作ったものだが、もとになるデータは第一次世界大戦のものを使用した。それによると連合国の船舶消耗量は総計で1196万トン、1年平均で281万トンであったという。
しかし第二次世界大戦が始まった1939年9月から1941年5月まで、イギリスや中立国の消耗船舶は670万総トンで、直近の1年では510万総トンに及んだ。ドイツによる、潜水艦Uボートを使った攻撃はイギリスなどにとって大きな脅威であった。
重要なのは、第二次世界大戦に入っての上記データを、日本の陸軍と日本郵船が所有していたことである。海軍がそれを持っていなかったのか。陸軍はあえてそれを伝えなかったのか。1941年10月の段階では、海軍の永野軍令部総長のように開戦に前のめりな首脳があえて新しいデータを無視したのか。
いずれも不明だが、時代遅れのデータをもとに新しい戦争を始めるためのデータが作られていたことは確かだ。新しいデータをもとに推計していれば、予想される日本の被害はずっと多くなるはずだった。
国家予算の4分の1をかけて「人造石油」の生産に踏み切ったが…
戦争は国の命運を左右する国策である。精度は究極まで高めなければならないが、十分とは言えなかったことが分かる。推計の精度が低いだけでなく、その推計値の解釈についても疑問が残る。
たとえば同月29日と30日、大本営政府連絡会議で企画院の鈴木総裁が石油に関する報告をした。企画院は内閣直属機関で、戦時統制経済の企画作成に当たった。石油を自給できない日本は、石炭から石油を造る人造石油に期待していた。ドイツが成功していたことに刺激を受けたもので、1937年に生産計画を立てた。
約8億円、当時の国家予算の4分の1近くを投じる壮大な計画で、1943年度末で年間200万キロリットルの生産を目標にしていた。石油需要の40%に及ぶ量である。政府、軍の首脳も期待していた。しかし開戦を前にしても生産は軌道に乗らなかった(結局、日本の人造石油の生産量の最高は1943年度の27万キロリットルだった)。
鈴木は、29日に人造石油には頼れないことを説明し、南方作戦すなわちインドネシアなどの産油地帯を押さえて石油が手に入れば自給体制は可能、と説明した。それによれば開戦1年目は供給が925万キロリットル、需要が670万キロリットル。255万キロリットルが残る。2年目はそれぞれ515万キロリットル、500万キロリットルと供給と需要がほぼ拮抗する。残りは15万キロリットルで、需要の11日分しかない。
それでも鈴木は「辛うじて自給体制を保持できる」としたが、本気でそう思っていたとしたら楽観的に過ぎる。