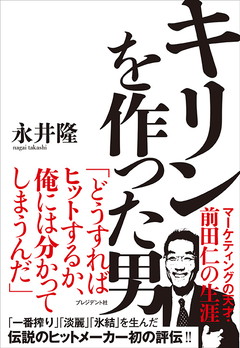運命の社内コンペ
前田チームの「一番搾り麦汁ビール」と、企画部とマッキンゼー混成チームの新商品。どちらを商品化するかを決める社内コンペが開かれた。
太田恵理子は、この時リサーチャーとして新商品の市場調査を担当していた。複数回実施した消費者調査と、社内テストの結果、前田チーム案の「一番搾り麦汁ビール」が「ぶっちぎりにスコアが高かった」と太田は証言する。
企画部・マッキンゼー混成チームの新商品は「キリン・オーガスト」という名前だった。
カタカナのネーミングから、若者がターゲットなのは明白だった。肝心のビールの中身はドライタイプで、よく言えば「スーパードライ」の大ヒットを受けた手堅い味。悪く言えば独創性に欠けていた。
それでも、デザインは非常にクオリティが高かった。日本広告史に残る超大物デザイナーが手掛けたとも言われている。その点でも、企画部・マッキンゼー混成チームの「本気度」は半端ではなかった。ちなみに広告代理店には博報堂がついていた。
一方の前田チームは、「一番搾り麦汁だけを使った贅沢なビール」を提出。軽快なドライでも、重厚なドイツタイプでもない、「ピュアな味わい」を追求していた。
この時点の名称は「キリン・ジャパン」。デザイナーは「丸井の赤いカード」で名を馳せた佐藤昭夫と、キリンデザイン部の望月寿城が担当。広告代理店は電通だった。
社内コンペが開かれたのは、89年の年末。
「大一番」は前田チームの圧勝に終わる。僅差を予想した人があっけなく感じるほどのワンサイドゲームだった。
プレミアムビールではスーパードライを止められない
コンペの結果を受け、すぐ経営会議が開かれた。その席上、前田チーム案「キリン・ジャパン」の商品化が正式に決定する。
ただ、ここで問題が持ち上がった。
「キリン・ジャパン」は、「ヱビス」のような高価格のプレミアムビールにするという。
一番搾り麦汁だけを使うと大幅なコストアップになる。前田チーム案にはその点で生産現場からの反発があった。
そのため経営会議で、コストが上がる分、商品価格を上げるという判断が下ったのである。
前田は会議に出席していたが、何も言えないまま、翌90年3月にプレミアムビールとして「キリン・ジャパン」を発売することが決定する。
「これでは勝てません。スーパードライを止める大型定番商品を作るのが、僕たちの目的だったはずです!」
会議の結果を持ち帰った前田に、さっそく舟渡が食ってかかった。舟渡は当初、一番搾り案には反発していた。ただ開発を進めるうちに考えを変える。一番搾り麦汁ビールのピュアな味わいに可能性を感じ、むしろ通常価格での販売を訴えていた。
価格の高いプレミアムビールは、販売量が限られる。サントリーの「ザ・プレミアム・モルツ」がプレミアムビール市場を創出するのはずっと先のことだった。
89年の時点では、プレミアムビールはまだ一般の消費者には浸透していなかった。
「ラガー」や「スーパードライ」と同じ通常価格で発売しなければ、大ヒットはない。
「前田さん、僕はこれから中茎さん(啓三郎専務、当時のビール事業本部長)のところに行って直談判してきます!」
そう宣言した舟渡を前田は止めた。
「やめとけ。とにかく、まず落ち着こう」
勝手な行動をとろうとした舟渡に、前田は怒らなかった。舟渡の考えをそのまま受け止め、むしろいつになく優しい眼差しで接していたという。
前田自身も通常価格で売るべきだと思っていた。そうしないと「スーパードライ」に対抗できないのはわかり切っている。だが、この時、前田は39歳。経営会議の決定を覆す力は持っていなかった。
その時、前田のマーケティング部第6チームが入るフロアのドアが静かに開き、大男が入ってきた。
「あっ!」
その男に気づくと、チームのメンバーが一斉に驚きの声を上げた。
その男は背筋をピンと伸ばし、前田のほうにズンズン迫ってくる。やがて前田の前にやってくると、前置きもなく言い放った。
「前田君、今日の経営会議の決定を、君はどう思う?」
この大男こそ、キリン社長の本山英世だった。